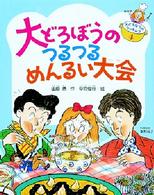目次
山村政策の展開と山村の存立基盤
中山間地域等直接支払制度の意義と制度的課題
山村における企業による農業参入
林業労働力確保対策の現段階―「緑の雇用」事業の評価を中心に
水資源開発と山村地域
伝統的建造物群保存地区山村と観光―岐阜県白川村と長野県白馬村を例に
長野県遠山郷における地域づくりの展開と「神様王国」
山村における生活様式の特色とその変容―長野県栄村秋山地区を事例として
山間地域集落の生活機能とソーシャル・キャピタル
奥三河地域における山間集落の現状からみた限界集落論―新城市鳳来地区3集落を事例として
非合併山村におけるむらづくりの可能性に関する一考察―岐阜県加茂郡東白川村を事例として
浜松市に併合された北遠州の山村・旧山窪村の変容過程とその存立基盤
平成の大合併と山村の再編成―中央日本を事例として
山村の経済問題と政策課題
山村政策への新たな視点
著者等紹介
藤田佳久[フジタヨシヒサ]
1940年生まれ。愛知大学文学部教授・愛知大学東亜同文書院大学記念センター長。理学博士。専攻:経済地理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
1
奥三河星座論や遠山郷神様王国論の藤田佳久先生、西野寿章先生に岡橋秀典先生らのお名前もあり、地理学の立場からの山村アプローチとなっている。山村とは集落社会を想起するイメージだが、「非限界集落」、「抵抗山村」(20ページ~)という呼称も登場し、必ずしも限界集落だけではないことが判明した。藤田先生の手書きによる図式化も素晴らしい(32ページ)。堤研二先生のソーシャル・キャピタル研究の問題点(226ページ)は、小規模の視点が弱いこと、上意下達になりがちなこと、質的データの扱い方という。生活人からの視点が重要か。2012/11/22



![Dr.コパの大開運タイミング風水カレンダー 〈2016〉 [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/43092/430927630X.jpg)