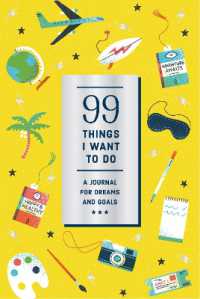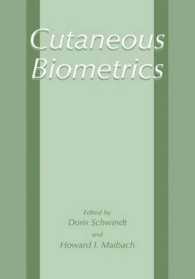出版社内容情報
色あざやかな花のポピー。その美しさで人間を魅了する一方、畑を荒らす厄介者とされ、麻薬の原料ともなってきた。生態から利用法、歴史まで、ケシ科植物(特にヒナゲシとケシ)と人間の豊かな関係をつづる。カラー図版約百点。
内容説明
色あざやかな花のポピー。その美しさで人間を魅了する一方、畑を荒らす厄介者とされ、麻薬の原料ともなってきた。生態から利用法、歴史まで、ケシ科植物(特にヒナゲシとケシ)と人間の豊かな関係をつづる。カラー図版約100点。
目次
第1章 ポピーとは何か
第2章 ケシ科
第3章 色
第4章 ポピーの生活環
第5章 農業のシンボルとしてのポピー
第6章 戦没者追悼のシンボルとしてのポピー
第7章 アヘン
第8章 そのほかの利用法と象徴的意味
著者等紹介
ラック,アンドリュー[ラック,アンドリュー] [Lack,Andrew]
イギリスのオックスフォード・ブルックス大学の生物学講師。研究分野は植物の生殖生態学と遺伝学、熱帯雨林の生態学、人間と環境の相互関係の歴史と哲学。1953年生まれ。オックスフォード在住
上原ゆうこ[ウエハラユウコ]
神戸大学農学部卒業。農業関係の研究員を経て翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
茅野
1
同シリーズ12冊目。「ポピー」という花名にあんまりピンと来なくてこの順になってしまったけど(ナンバリングされていないので、関心の赴くまま適当な順で読み進めている)、ケシのことかと気付いて手に取った。分布や用法やシンボルなど盛り沢山で、このシリーズで特に面白かった一冊かも。 個人的にはチェルニャコフ演出のオペラ『イーゴリ公』やバレエ『赤いけし』などからロシアのイメージ強かったケシの花だけど、特に言及無し。『イーゴリ公』聴きながら読みました。まあ、順当にイギリス、中国、アフガニスタンですね。2023/08/23
ぞだぐぁ
1
ヒナゲシとケシが歴史的にどのような文化的な役割を果たしていたかを紹介している本。交雑など生物的な話から材料となってしまう麻薬についての話も。2022/08/03
木倉兵馬
1
もともとは麦畑の雑草にすぎなかったポピー。しかしその文化は幅広く花咲いていった。負傷兵や戦死者を悼む象徴の花 としてのポピーは知らなかった。一方でアヘンをつくるものでもあるため、その問題についても述べられていた。2022/07/23
雉彦
0
ふと目に入ったので図書館で借りた。 分類学的な見方から文化的にどういう扱われ方をしたか、歴史の授業で見たアヘン戦争の勃発など、名前を知っているだけだった花の様々な側面が見られてよかった。 イギリスの出版社から出ているシリーズの邦訳版もシリーズ化してるとは知らなかったので、他の植物の文化誌も読んでいきたい。2023/03/11