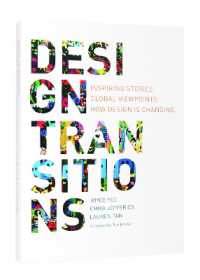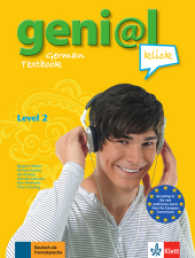- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
いかにして古代からの言葉が消えていくのか。パプアニューギニアの村ガプンの人々と寝食を共にし、ネイティブ原語を30年間にわたって調査してきた言語人類学者によるルポルタージュ。西欧文明が村から奪っていったものは。
内容説明
グローバリズムに呑み込まれゆくパプアニューギニアの先住民族の村で、調査を続けた人類学者が30年にわたって見つめた、ある「終わり」のルポルタージュ。
目次
我々が吸う空気
湿地の村
まずは教師をつかまえる
モーゼスの計画
贈与の義務
ガプンでの食事
「ここから出ていく」
虹の彼方に
詩的な悪態
肝臓の問題
若者のタヤップ語
危険な生活
誰がモネイを殺したか?
ルーク、手紙を書く
地獄への旅
言語が消滅するとき、実際には何が消えるのか?
終わりについて
著者等紹介
クリック,ドン[クリック,ドン] [Kulik,Don]
1960年生まれ。スウェーデンのルンド大学で言語学と人類学を修め、ストックホルム大学で人類学の博士号を取得した。パプアニューギニア、ブラジル、スカンジナビアでフィールドワークをおこない、現在はウプサラ大学で人類学の教授を務めている
上京恵[カミギョウメグミ]
英米文学翻訳家。2004年より書籍翻訳に携わり、小説、ノンフィクションなど訳書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroo Shimoda
19
言語はコミュニティではなくアイデンティティを作っており、個人個人で違う。言語は共有物ではなく所有物という考え方は面白い。2020/03/30
takeapple
17
パプア・ニューギニアのタヤップ語を話す人々の住むガプンという村に住み着いて参与観察を行ったスウェーデン人の人類学者ドン・クリックの本。現代のヨーロッパ人が全くの未開のジャングルの村でどんな生活をしてどんな発見をするのか興味深く読んだ。それにしても人の幸せというか人生ってなんなんだろう?他の文化に私たちが与える影響は何と考えたら良いのだろう。著者がありきたりのヒューマニズムや人類学的常識に囚われていないところが好きだ。最後の献辞も良いし、消滅しかかっているタヤップ語についての思いも共感できる。2020/04/26
CCC
15
言語学者のミクロ視点ドキュメンタリーといった感触。フィールドワークの苦労話がメインになってた気もしたけれど面白かった。工業製品をねだられたり、食事がおいしくなかったり。殺人事件に巻き込まれる展開も。一番印象深かったのは村の改造計画が失敗するエピソード。世界中で起こっているありふれた悲劇なのかもしれないが、もの悲しい気持ちになる。2020/03/03
ぽけっとももんが
13
言葉の消滅というのは、その言葉を話す住民が減っていくということ。ただそれは村人の人数が減るということではなかった。タヤップ語を使うガプンの村人は減るどころかどうやらこどもたちがたくさんいるらしい。ただ、若い人たちがタヤップ語を使わなくなったのだ。他の村とも共通する、そしてたぶん都会を思わせるトク・ピシンで話す。タヤップもわかるけれども使わない。次世代にはタヤップはもう伝わらない。奔放な彼らの育児や死生観、そして恐るべき食生活。方言、そして日本語の未来を憂いながらも、とても楽しく読んだ。2020/09/22
Gamemaker_K
10
消滅危機言語タヤップ語に関するフィールドワーク苦労譚。言語の話を超えたところが面白くて、特に大きな事件に巻き込まれる最後の方は不謹慎ながら手が止まらなかった。期待をはるかに超えた一冊。・・・若い人がタヤップ語を知っているのに使わなくなる理由が興味深かった(理由:長老による誤用への罵倒)。知ってる人は、知らない人に対して寛容であるべきだ。知ってることだけなら何もえらいことではないと思うからだ。2020/05/30