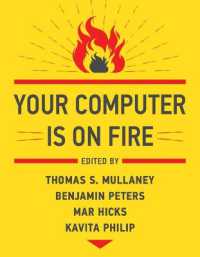出版社内容情報
ギリシア・ローマ・ゲルマン・北欧・ケルト神話や博物誌、人狼伝承、聖人信仰、エンブレム(紋章)、古典的な造形表現、寓話・童話、民間伝承、俗信、言語表現などに登場する、狼の社会的・象徴的・歴史的意味とその変容を、数多くの貴重な図像解読する名著。
目次
古代の神話体系
ローマの狼
野獣より強い聖人
動物誌のなかの狼
イザングラン―笑いのための狼
人狼と魔女
呼称とエンブレム
寓話と童話
農村部の野獣
ジェヴォーダンの「獣」
近代の信仰と俗信
現代の狼
著者等紹介
パストゥロー,ミシェル[パストゥロー,ミシェル] [Pastoureau,Michel]
1947年、パリ生まれ。国立古文書学校卒。フランス国立図書館メダイユ部門主任をつとめたのち、国立高等実習研究院、ついで国立高等社会科学研究院主任教授、フランス紋章・印章学会会長などを歴任した。著書『われわれの記憶の色』(2010年)でメディシス賞(評論部門)受賞
蔵持不三也[クラモチフミヤ]
1946年、栃木県今市市(現日光市)生まれ。早稲田大学第1文学部フランス文学専攻卒、パリ第4大学(ソルボンヌ大学)修士課程修了(比較文化専攻)、社会科学高等研究院博士課程修了(民族学専攻)。早稲田大学人間科学学術院教授やモンペリエ大学客員教授をへて、現在早稲田大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
らぱん
51
大著。文献資料から時代による狼の扱われ方の変遷で図版も多い。12~13世紀にイギリスとフランスで、宗教的道徳的な教訓のネタに使うため動物誌が流行った。中でもフランス上流階級では、動物の特性を活かし、愛の戦術に応用し異性の心の掴み方を伝授する動物誌が大人気だったらしい。眉唾物の狼の生態を引用した口説き文句がかなり可笑しいのだが、残念なことにそのあたりの記載は少ない。 暗黒の中世よりも近世以降、狼は悪魔そのものや眷属としての地位を獲得し、ネガティブイメージが定着し、性的メタファーにも使われ大活躍する。↓2020/01/12
ワッピー
40
ヨーロッパの原初神話~ローマの建国神話、キリスト教下のイメージ、中世における動物誌、宮廷文学パロディの狼、狼に由来する地名や人名、15世紀以降の農村での現実的な脅威、有名な狼の連続人間殺傷事件、そして近世・現代にいたるイメージの変遷を扱っています。これまで支配的だった「狼=悪」の構図は自然をキリスト教的神の支配下に置くために狼を貶めた結果のようにも感じます。豊富な図版を楽しみましたが、一方で図の説明もまた多く、段組の本文と紛れやすかったので、説明文に枠をつける、文字色を変えるなど更なる工夫がほしいところ。2021/05/15
人生ゴルディアス
6
狼について、ローマ建国神話からキリスト教による扱い、また貴族の紋章に用いられるとか、ケルト、北欧神話における狼の話など、思い付きそうな話題について一通り解説が入る。網羅的なんだけど、『熊の歴史』よりあっさりしてたかな…。『熊』のほうは結構読み応えあった。で、本書は誤字脱字がひどい。ラグナロクをナグラロクと記述していたり、「味あわせる」とか書かれていて(味わわせる、が正しい)元早稲田大学教授の文章です…? 真面目に本を作れと思う。2021/04/04
スターゲイザー
3
沢山の絵が紹介されていて視覚的にわかりやすくて良い。ヨーロッパ社会において、狼は神話や寓話などといった様々な形で語り継がれる動物だということがわかりました。2023/09/12
てつこ
3
紋章や動物誌の研究者が、狼を文化史の一要素として捉え、欧州の神話や寓話、民間伝承から狼の象徴的意味を解説する。ローマの時代から狼は残酷で不潔で淫奔を表しており、狐物語で愚かなイメージが追加される。魔女狩りの時代には人狼など悪魔の使いとしたネガティブな印象が付け加えられた。また17-19世紀、ジェヴォーダンの獣に代表されるような事件は人々の恐怖を煽り、狼への恐れをピークにさせた。印欧語族では狼を指す呼称が光や輝きを意味するleuk-あるいはwulkから派生しているのが面白い。闇の中で光る目を表すらしい。2021/12/27
-

- 電子書籍
- 3か月で自然に痩せていく仕組み - 意…