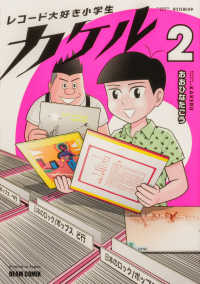出版社内容情報
19世紀、ヴィクトリア時代の社会派ジャーナリストの雄メイヒューが、密着取材。呼売商人、故買屋、煙突掃除夫……。繁栄のさなかに巣食う貧困のどん底に生きる人々があみだす珍商売・奇商売の数々。当時の庶民の生活と風景が甦る。
内容説明
一九世紀ロンドン、ヴィクトリア時代―階級社会の最下層で暮らす労働者たちの貧困、生きることへのどん欲さ、諍(いさか)い、笑い…庶民のリアルな姿と肉声をつぶさに観察、克明に描いた英国生活誌の不朽の名著。
目次
ローズマリー・レーン
スミスフィールド・マーケットの中古品売り
生きた動物を売る街頭商人
犬の「捜し屋」―ある「ぺてん師」の生涯
偽物の鳥を売りつける小鳥屋の術策
鳥の巣を売る街頭商人
テムズ川のビール売り、あるいはパール売り
ぼろ、壊れた金物類、ビン、ガラス、そして骨を買い取る街頭商人
「ぼろとビン」を扱う店、及び「中古船具」を扱う店
台所のごみ、油脂及び脂汁の回収業者〔ほか〕
著者等紹介
メイヒュー,ヘンリー[メイヒュー,ヘンリー][Mayhew,Henry]
1812年英国生まれの著述家。1887年、気管支炎のためロンドンで死去
植松靖夫[ウエマツヤスオ]
上智大学大学院文学研究科英米文学専攻博士後期課程修了。東北学院大学文学部教授。東北大、弘前大、名古屋外国語大学大学院などでも教鞭を執る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Miyoshi Hirotaka
26
『オリーバー・ツイスト』、『レ・ミゼラブル』、『天井桟敷の人々』など産業革命で変容した社会を背景とした作品には共通点がある。それは、格差、犯罪、リスクの高い選択だ。そのエビデンスが本書。特に下水道は『レ・ミゼラブル』で逃走路として使われただけでなく、有価物の回収場所だった。子供を含む最底辺の人々が廃棄物のリサイクルチェーンを担っていた。あらゆるものを商機と捉え、逞しく生きる姿に感動と尊敬の念を覚える。一方、二世紀が経過。歴史は繰り返さないが韻を踏む。わが子孫がここまで追い込まれないよう知恵を絞りたい。2024/10/25
tosca
18
上下巻共、職業別に人々の生活を紹介していて、実際のインタビューで語られた声も交えているので、当時の街の雰囲気や人々の生活の様子が臨場感たっぷりに伝わってくる。下巻は職業がさらにハードになる。犬の糞集め、ボロ集め、台所のクズや油脂の回収、骨集め、ドブさらい等々。著者はその時代の人なので、上から目線で失礼な表現があるのは仕方ないのだが、それでもよく現場に足を運んで取材したなぁと感心する。古くてもルポルタージュなので、過酷な労働、劣悪な環境下で酷使される幼い孤児や貧しい子供達の話は辛い。2020/09/29
氷菓子
4
現代の格差とは比べものにならないくらい、貧しい人の生活が厳しい。河川や排水溝でドブさらいをして拾った金属を売る人、犬の糞を集めて売る人など、稼ぎを聞くまでもなく生活の厳しさが伺える。それでも「救貧院」には絶対に入りたくないと語る人が多いが、そんなに嫌われる福祉施設は一体どんな環境なのだろう。色々な動物や鳥の生息地、行動様式を把握して需要のあるものを捕獲して売る街頭商人の話は、貧しくて大変というよりも、博学ですごいなという印象を受けた。2022/02/23
颯奏
3
小説の舞台は中流階級以上な場合が多いのでこの本を読むとロンドン…ぇぇぇ…な気持ちになりますね。下層民の暮らしはこうだったのか!と。読んで良かったです。2015/07/05
W
2
ネズミや排水溝の話のボリューム感に、ロンドンを舞台にしたエドワード・ケアリーの『堆塵館』がああいうストーリーになるのも納得。七歳?の泥さらいの男の子が〝神〟は何となく分かるけど〝信仰〟の意味は分からないというのが印象的。ねずみ虐め、ちょっと見てみたい。(CGで)2024/04/16
-
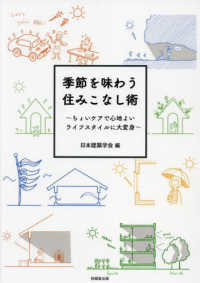
- 和書
- 季節を味わう住みこなし術
-

- DVD
- グランドファーザー 哀しき復讐