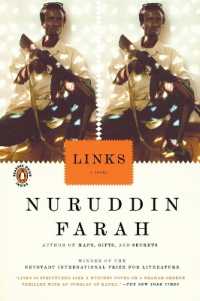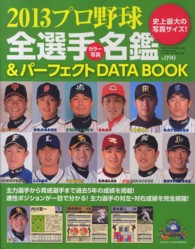出版社内容情報
記憶と書物を結ぶ糸をたどって
書物の出現に始まる「読書」という営為と「記憶」という精神の働きの間にはどのような歴史が刻まれてきたのだろうか──本書は西欧の古代・中世、そして日本は江戸・明治を中心に書物のかたちの変遷(特に西欧中世における「索引」の誕生に注目)と、それに伴う読書のかたちの変容(音読から黙読へ)を「記憶」を縦糸とした文化史として跡づける試みである。日本においては、江戸に行われて明治まで続いた「素読」(音読)が文字(漢字)と音を意味以前に記憶として心身にしみこませるメソッドであった消息を明らかにし、ついで庶民による草双紙の読まれ方、書物に向けられた儒者・漢詩人の深い愛、あるいは翻訳小説『あひびき』の文体が読書人に与えた驚き等、読書の変容を豊富な逸話を交えて辿った後、西行が月蝕の歌に詠み込んだと思われるある秘義に迫り、地名に執着した柳田国男と「記憶術」の意外な関連に及ぶ。西欧においては、修道士の読書がいかに瞑想と記憶に結びついていたかを探り、聖書と索引誕生の知られざる関係を解き明かし、さらには魂の探求を続けたアリストテレス、アウグスティヌス、ベルクソンの思索を通じ、あらためて「読書」という経験の深さを読む者の心に呼び起こす。
内容説明
書物の変遷と読書の変容。さらに両者の織りなす記憶という人間精神の多様ないとなみを、東西の知の歴史に重ね合わせた綺想の文化史。
目次
1 最初の読書体験
2 比類なき記憶のもたらした幸と不幸
3 読書の変容―素読から草双紙を経て近代読者の成立まで
4 中世ヨーロッパ修道院における読書法
5 索引の誕生
6 記憶術とは何か
7 西行 月の記憶
8 柳田国男 地名の記憶
著者等紹介
鶴ヶ谷真一[ツルガヤシンイチ]
1946年東京に生まれる。早稲田大学文学部卒業。編集者として主に翻訳書の編集にたずさわる。著書に『書を読んで羊を失う』(白水社、日本エッセイスト・クラブ賞、増補版は平凡社ライブラリー)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あきあかね
デビっちん
チェアー
izw
takao