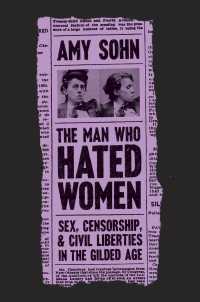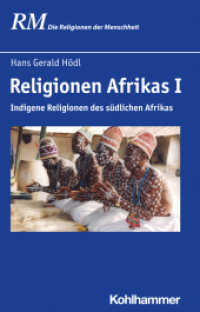出版社内容情報
ポピュリズム的ナショナリズムと高度産業社会に充満する不安を理解するための必読書。フランシス・フクヤマ、ラグラム・ラジャン推薦
内容説明
自由主義と重商主義の攻防。それともポピュリズム?
目次
より良いバランスを取り戻す
国家の仕組み
欧州の苦闘
仕事、産業化、民主主義
経済学者と経済モデル
経済学上のコンセンサスの危機
経済学者、政治、アイデア
政策イノベーションとしての経済学
何がうまくいかないのか
グローバル経済の新たなルール
将来に向けた成長政策
政治こそが重要なのだ、愚か者!
著者等紹介
ロドリック,ダニ[ロドリック,ダニ] [Rodrik,Dani]
1957年、トルコ・イスタンブールに生まれる。米ハーバード大学を卒業後、プリンストン大学でMPA、Ph.D.をそれぞれ取得。プリンストン高等研究所(IAS School of Social Science)教授などを経て、ハーバード大学ケネディ・スクール教授。専門は国際経済学、経済成長論、政治経済学
岩本正明[イワモトマサアキ]
1979年生まれ。大阪大学経済学部卒業後、時事通信社に入社。経済部を経て、ニューヨーク州立大院で経済学修士号を取得。通信社ブルームバーグに転じて独立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroo Shimoda
8
貿易を通し社会的不平等が伝播する。とすれば、サービス残業しまくりの日本が相対的な低コスト品を輸出してくるのは労働環境を大事にする国からすれば不平等な戦争であり、障壁を作るのも当然。2019/09/29
hidek
4
世界は分断と連携を繰り返す。前回は金本位制による国際連携への反発からファシズムや共産主義が台頭した。今回も異教徒や移民、富裕層等を矛先に分断が始まっている。著者はこの責任の一端が経済学者にもあると批判する。多くが国際化の負の側面をあえて伝えず、際限の資本の自由を推し進めた為だ。目指すべきは国内経済を秩序あるものにしつつ、社会を民主的なルールに沿うよう調整していくことであると云う。その他にも学問としての経済学、経済成長における自由化や構造改革の功罪、新興国の発展の鍵なども議論し世界経済情勢を俯瞰できる一冊。2019/09/26
人生ゴルディアス
3
滅茶苦茶面白かった。グローバリゼーション・国家主権・民主主義のトリレンマの指摘だけでもう面白い。自由競争がイノベーションを生み出し、国家運営にたった一つの正解がないのなら、個々の国ごとに様々な制度を試し競争すべきで、画一的な国際制度を求めるグローバルガバナンスは誤りであり、グローバルガバナンスは明らかに各国の政策を縛り上げることになる。極端な例がEUで、崩壊の瀬戸際に立たされている。自由主義は雇用を生み出さず重商主義は雇用を生み出すとか、関税合戦よりかは国内補助金合戦のほうがましとか、目から鱗の指摘が多い2020/01/10
デンプシー
2
スローバリデーションを国際政治経済学的に説いた本書だったが、リベラリズム・革新主義への反駁にも思えた。つまり、各国が歴史的に積み重ねてきたルール(規制・制度)をぶち壊してまっさらにした上に。ワシントン・コンセンサスのような普遍的なルールを据え置いても上手くいくわけがない、もっと穏便に、テーラーメイドな制度にしましょうねという、聞き覚えのある展開が聞こえてくるようだった。また、産業政策・経済政策における国家の意義にも触れていて時代の変化を感じた。ところで「貿易戦争の経済学」はミスリードなタイトルだと思う…。2024/03/28
Kooya
2
規制緩和による「過度な」グローバリゼーションを批判した本。貿易をはじめ多様なテーマについて論じている。市場が滞りなく機能するためには適度なルールが必要だという主張は、制度派経済学に依拠した考えだと感じた。また、経済学を現実社会に適用する際は所与の状況に応じて使用するモデルを使い分けるべきだという主張は、モデルはあくまでも実体経済に従属するものということを暗示している点で納得できた。(コメント欄に続く)2023/02/06
-
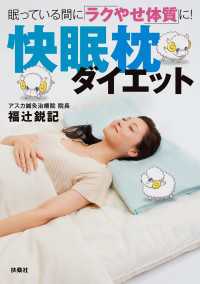
- 電子書籍
- 快眠枕ダイエット 雑学・実用BOOKS