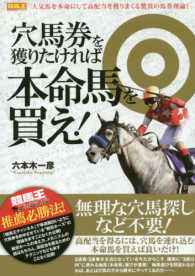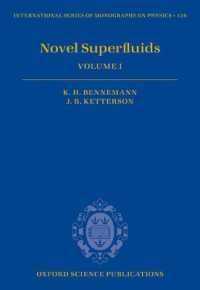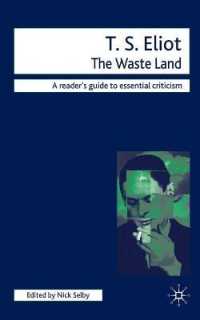出版社内容情報
「解放の思想」の原点へ
「批判理論」は、1920年代から30年代にかけて、フランクフルトの社会研究所に集まった思想家たちによって打ち立てられた。所長をつとめたホルクハイマー以下、アドルノ、フロム、マルクーゼ、ベンヤミン、ハーバーマスと、その名を挙げていけば、そこに20世紀社会科学の荘厳な群像劇が立ち現れる。
彼らの活動が「批判理論」としてではなく「フランクフルト学派」として記憶されたことが本書の大きな出発点になっている。社会をトータルに対象化し、新たな解放の思想を提示する「批判」という手法は、自家中毒をおこして(否定弁証法)、解体してしまったのではないかという問題意識である。
フランクフルト学派から批判理論へ――。これが本書の大きな柱となる。そこで浮上してくるのは、人物ではなく概念だ。とりわけ、「疎外」と「物象化」に大きな光が当てられる。
批判理論はそもそもプロレタリアートのための「解放の思想」であり、実践と結びついて意味がある。このため本書では「疎外」も「物象化」も簡潔に定義され、読者が現実に立ち向かうための武器として与えられる。閉塞感深まる日本を捉える一冊。
スティーヴン・エリック・ブロナー[ブロナー]
著・文・その他
小田 透[オダ トオル]
翻訳
内容説明
「解放の思想」の原点へ。批判的社会理論を“疎外”と“物象化”を中心に、現実に立ち向かうための「武器」として再生させる画期的入門。
目次
イントロダクション―批判理論とは何か?
第1章 フランクフルト学派
第2章 方法の問題
第3章 批判理論とモダニズム
第4章 疎外と物象化
第5章 啓蒙された幻想
第6章 ユートピアの実験室
第7章 幸福な意識
第8章 大いなる拒絶
第9章 諦念から再生へ
第10章 未完の課題―連帯、抵抗、グローバル社会
著者等紹介
ブロナー,スティーヴン・エリック[ブロナー,スティーヴンエリック] [Bronner,Stephen Eric]
1949年生まれ。米カリフォルニア大学バークレー校で博士号取得。その後、米ラトガーズ大学政治学部で教鞭を執り、同大でもっとも権威あるボード・オブ・ガバナーズ・プロフェッサーのほか、ユネスコと連携する「虐殺予防と人権」のための研究プログラム執行委員を歴任。ニュースクール・フォー・ソーシャルリサーチ(NSSR)訪問教授も務めた。2011年に「中近東平和賞」を受賞するなどアメリカを代表する政治学者
小田透[オダトオル]
1980年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。カリフォルニア大学アーバイン校で博士号(比較文学)取得。静岡県立大学特任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シッダ@涅槃
代理
ふんと
_ray4472