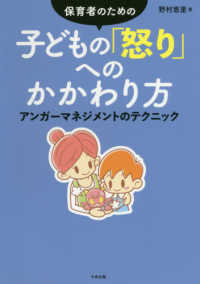出版社内容情報
非西洋圏の「記憶」の問題に着目し、口承文化と文字文化の中間段階にあるイメージの機能に光を当てる。
内容説明
文字なき社会において「記憶」はいかに継承されるのか。西洋文化のかなたに息づく「記憶術」から人間の「思考形式の人類学」へと未踏の領域を切り拓くレヴィ=ストロースの衣鉢を継ぐ人類学者による記念碑的著作。本邦初紹介。
目次
第1章 人類学者ヴァールブルク、あるいはあるユートピアの解読―イメージの生物学から記憶の人類学へ(ヴァールブルク―視覚的象徴とキマイラ;忘却された根 ほか)
第2章 アメリカ先住民の記憶術の形―絵文字とパラレリズム(絵文字の解読―ダコタ聖書;絵文字とシャーマンの歌―クナ族の例 ほか)
第3章 記憶、投射、信念、あるいは話者の変容(複雑な話者;投射と信念 ほか)
第4章 分かちえぬキリスト(アパッチ族のキリスト;ドニャ・セバスティアーナ ほか)
著者等紹介
セヴェーリ,カルロ[セヴェーリ,カルロ] [Severi,Carlo]
1952年生まれ。ミラノ国立大学で哲学を修めたあと、パリの社会科学高等研究院(EHESS)にて人類学を学び、クロード・レヴィ=ストロースのもとで博士号を取得。現在、同研究院社会人類学講座教授、フランス国立科学研究センター(CNRS)教授を務めるほか、社会人類学研究所メンバー、パリのケ・ブランリ美術館研究・教育部門協力者を務める
水野千依[ミズノチヨリ]
1967年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。現在、青山学院大学文学部教授。専門はイタリア・ルネサンス美術史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
misman
takao
中村蓮
路雨
-

- 洋書
- NØT NØ…