出版社内容情報
ドイツの実力派による〈トーマス・マン〉賞受賞作
大学を定年退官した古典文献学の教授リヒャルトは、アレクサンダー広場でアフリカ難民がハンガーストライキ中とのニュースを知る。彼らが英語で書いたプラカード(「我々は目に見える存在になる」)について、リヒャルトは思いを巡らす。
その後、オラニエン広場では別の難民たちがすでに1年前からテントを張って生活していることを知る。難民たちはベルリン州政府と合意を結んで広場から立ち退くが、彼らの一部は、長らく空き家だった郊外の元高齢者施設に移ってくる。
難民たちに関心を持ったリヒャルトは、施設を飛び込みで訪ね、彼らの話を聞く。リビアでの内戦勃発後、軍に捕えられ、強制的にボートで地中海へと追いやられた男。命からがら辿り着いたイタリアでわけもわからず難民登録されたが、仕事も金もなくドイツへと流れてきた男。
リヒャルトは足繁く施設を訪ね、彼らと徐々に親しくなっていく。ドイツ語の授業の教師役も引き受け、難民たちとの交流は、次第に日常生活の一部となっていくが……東ドイツの記憶と現代の難民問題を重ね合わせ、それぞれの生を繊細に描き出す。ドイツの実力派による〈トーマス・マン賞〉受賞作。
内容説明
どこへ行けばいいかわからないとき、人はどこへ行くのだろう?退官した大学教授リヒャルトは、ベルリンに辿り着いたアフリカ難民に関心を抱く。難民たちとの交流は、次第に彼の日常生活の一部となっていくが…東ドイツの記憶と現代の難民問題を重ね合わせ、それぞれの生を繊細に描き出す。ドイツの実力派による“トーマス・マン賞”受賞作。
著者等紹介
エルペンベック,ジェニー[エルペンベック,ジェニー] [Erpenbeck,Jenny]
1967年ベルリン(当時は東ベルリン)生まれ。1985年に高校を卒業後、二年間の製本職人の見習いを経て、舞台の小道具係や衣装係として働く。1988年から90年にかけて、フンボルト大学で演劇学を学ぶ。1990年からはハンス・アイスラー音楽院でオペラの演出を学び、94年以降、舞台監督としてさまざまなオペラの演出を手がける。同時期に執筆活動を開始し、99年、『年老いた子どもの話』(河出書房新社)で小説家としてデビュー。2015年に発表した『行く、行った、行ってしまった』はベストセラーとなり、翌年度トーマス・マン賞を受賞。これまでに12の言語に翻訳されている。2017年、ドイツ連邦共和国十字小勲章を受章。その他受賞歴多数
浅井晶子[アサイショウコ]
1973年大阪府生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位認定退学。訳書多数。2003年マックス・ダウテンダイ翻訳賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
NAO
ヘラジカ
優希
nobi
-

- 電子書籍
- スニーカー学 atmos創設者が振り返…
-
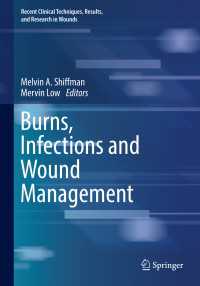
- 洋書電子書籍
- Burns, Infections a…







