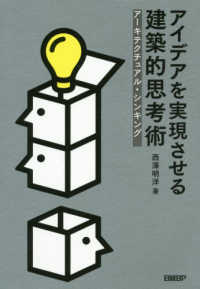出版社内容情報
動物なのか死体なのか、それが問題で……。東日本大震災に見舞われた10人の高校生たちは、「生存確認」の声を響かせつづける!
【著者紹介】
1961年3月22日、山梨県甲府市生まれ。演出家、現代美術アーティスト。
内容説明
東日本大震災に見舞われた10人の高校生たちが生存確認の声を反響させてゆく表題作のほか、ポストドラマ時代のドキュメンタリー児童劇『「教室」』を併録。第58回岸田國士戯曲賞受賞作品。
著者等紹介
飴屋法水[アメヤノリミズ]
1961年山梨県生まれ、神奈川県育ち。唐十郎主宰の状況劇場を経て、東京グランギニョル、M.M.M.を結成し、機械と肉体の融合を図る特異な演劇活動を展開。90年代は活動領域を美術へと移行するも、95年のヴェネツィア・ビエンナーレ参加後に作家活動を停止。同年に「動物堂」を開店し、動物の飼育・販売を始める。2005年、24日間箱の中に自身が入り続ける「バングント」展で美術活動を、07年に平田オリザ作『転校生』の演出で演劇活動を再開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 4件/全4件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りえこ
27
そんなにきつい描写があるわけではないのに、なんだかとても悲しくなるというか、辛くなる。地震の事を思い出すし、空気が流れている。2014/05/22
Saku
17
3.11で被災したいわきの高校生10人が実名で演じた戯曲。しかも作演出が飴屋法水。敷かれたブルーシートと10脚の椅子。直接的な表現はあまり出てこないけれど、生きていることと死ぬということについて考えてしまう。 『それ以前だよ。』 あのとき、彼らは何を見たのだろう、その後何を見て来たのだろうか。 2016/01/22
かんがく
12
岸田戯曲賞。著者が福島の高校生たちとともに作った戯曲。なんとその高校生たちは95年生で私と同い年だ。そこで自分が高校時代の演劇部で参加したワークショップで、震災を題材にした演劇をやらされて、被災者ではない自分たちが起きて間もない震災を演劇のテーマとすることに違和感と躊躇を感じたのを思い出した。一方、この戯曲の制作と上演には「当事者」たちが参加している。その点が選評にもあったように、戯曲としての評価を難しくさせていると感じてしまった。2024/05/12
ふう
10
飴屋法水の第58回岸田國士戯曲賞受賞作。生と死を身近に、それでいて突き放したように描いていたが、あの時の彼らがあの場所で演じたからこそ成り立つものって感じで残念ながら正直あまりピンと来ず。なんとなく登場人物全員がずっと正面向いて喋ってるような、勝手にそんな真摯すぎる(?)受け止め方をしたせいだろうか。うーん、併録されてる「教室」のがまだよかったかなぁ。きっと単純に私が飴屋法水に合わないだけかも(と強引に結論)。2017/08/02
しまりす
9
いわき総合高校の生徒達と創られた戯曲。まさにこの作品を上演するために稽古中な私ですが往復する度にこの作品に込められたモノを感じ、さてどう表現すると成立するかと模索の日々です。すでにおぼろげになる部分も出てしまったあの日と日常の対比とてもヒリヒリ痛みます。西日本豪雨の映像があの日と重なり思い出さざるを得ない。今回上演の意義があるように感じ身を引締めて表現しようと思います。2018/07/20
-

- 電子書籍
- 【実録】読者の笑撃体験!~桜木さゆみ編…