出版社内容情報
ブルトンが絶讃した狂気と幻覚の手記
ペルシア語文学史上に現われた「モダニズムの騎士」による、狂気と厭世に満ちた代表作を含む中短篇集。「人生には徐々に孤独な魂をむしばんでいく潰瘍のような古傷がある」――生の核心に触れるような独白で始まる「盲目の梟」。筆入れの蓋に絵を描くことを生業とする語り手の男が、心惹かれた黒衣の乙女の死体を切り刻みトランクに詰めて埋めにいくシュルレアリスム的な前半部と、同じ語り手と思しい男が病に臥しての「妻殺し」をリアリスティックに回想する後半部とが、阿片と酒精、強烈なペシミズムと絶望、執拗に反復されるモチーフと妄想によって複雑に絡み合う。ドストエフスキーやカフカ、ポーなどの西欧文学と、仏教のニルヴァーナ、イランの神秘主義といった東洋思想とが融合した瞠目すべき表題作とさまざまな傾向をもつ九つの短篇に加え、紀行文『エスファハーンは世界の半分』を収める。解説=中村菜穂
【目次】
内容説明
「人生には徐々に孤独な魂をむしばんでいく潰瘍のような古傷がある」―生の核心に触れるような独白で始まる代表作の中篇「盲目の梟」。筆入れの蓋に絵を描くことを生業とする語り手の男が、心惹かれた黒衣の乙女の死体を切り刻みトランクに詰めて埋めにいくシュルレアリスム的な前半部と、同じ語り手と思しい男が病に臥しての「妻殺し」をリアリスティックに回想する後半部とが、阿片と酒精、強烈なペシミズムと絶望、執拗に反復されるモチーフと妄想によって複雑に絡み合う―。ドストエフスキーやカフカ、ポーといった西欧文学と、仏教のニルヴァーナ、イランの神秘主義といった東洋思想とが融合した瞠目すべき表題作と、さまざまな傾向をもつ9つの短篇に加え、古都への旅を綴った紀行文『エスファハーンは世界の半分』を収める。
著者等紹介
ヘダーヤト,サーデク[ヘダーヤト,サーデク] [Hed ̄ayat,〓 ̄adeq]
1903‐1951。1903年、イラン・テヘラン生まれ。テヘランの学校でヨーロッパ式の教育を受け、ベルギー、フランスへ遊学。イラン古来の伝統に深い関心を寄せる一方、ポーやカフカ、チェーホフなどの外国文学に傾倒、なかでもカフカについては自ら作品を(仏訳から)翻訳し、作品論を執筆している。1930年に第一短篇集『生埋め』を上梓し、以後短篇集『三滴の血』(32)、『明暗』(33)『野良犬』(42)、中篇小説『ハージー・アーガー』(45)などを刊行。インド滞在中に書き上げられた『盲目の梟』(37)は代表作として名高い。また、ハイヤーム『ルバイヤート』の小川亮作訳が底本とした選集を編んだことでも知られる。1951年に逗留先のパリでガス自殺を遂げた
中村公則[ナカムラキミノリ]
慶應義塾大学大学院博士課程修了(東洋史学)。2013年歿(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Greatzebra
Porco
CCC
ふゆきち
sugsyu
-

- 電子書籍
- Men’s PREPPY 2025年3…
-
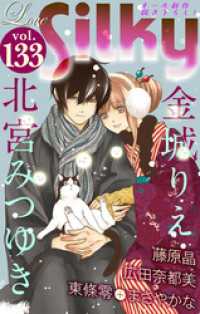
- 電子書籍
- Love Silky Vol.133 …
-
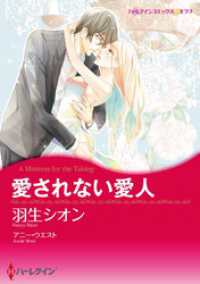
- 電子書籍
- 愛されない愛人【分冊】 12巻 ハーレ…
-

- 電子書籍
- 週刊女性 2022年 08月16日号
-
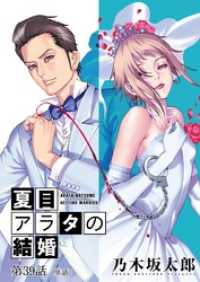
- 電子書籍
- 夏目アラタの結婚【単話】(39) ビッ…




