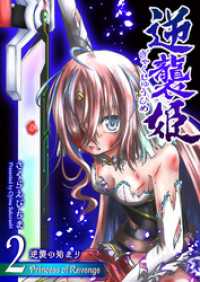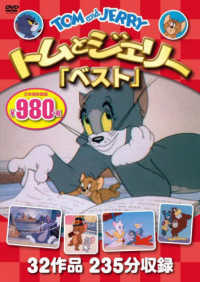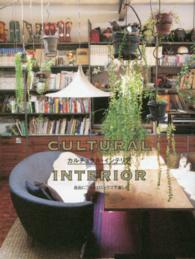出版社内容情報
非人間的な管理体制で患者を支配する精神病院。精神の自由を賭けた戦いを挑む、不屈の反逆者を描いた名作。
【著者紹介】
1935~2001年。アメリカの作家。精神科病棟で働いた経験をもとに書きあげた小説『カッコーの巣の上で』(1962)がベストセラーとなる。舞台化、映画化も大ヒット。カリフォルニアでヒッピー・コミューンを設立、サイケデリック・バスの全米ツアーや、麻薬体験の実演、トリップス・フェスティバルの開催など、60年代若者文化に多大な影響を与えた。
内容説明
刑務所の農場労働を逃れるため精神異常を装い、委託患者として精神病院にやってきた赤毛の男マックマーフィ。そこではラチェッド婦長が厳格な規則と薬物投与で患者たちの人間性を奪い、病棟を管理支配していた。マックマーフィは笑いと不屈の反抗心を武器に婦長に戦いを挑み、その姿に無気力状態にあった患者たちも自由の喜びと勇気を取り戻していくが…。体制への反逆と精神の自由を求める戦いを描いて鮮烈な感動を呼ぶ、20世紀アメリカ文学を代表する名作。
著者等紹介
キージー,ケン[キージー,ケン] [Kesey,Ken]
アメリカの作家。1935年、コロラド州に生まれ、オレゴン大学卒業後、スタンフォード大学創作科に進む。薬物実験のボランティアとしてLSDなどの麻薬を体験、さらに精神科病棟の夜勤で得た経験をもとに『カッコーの巣の上で』を書きあげ、1962年に出版されるや大ベストセラーとなる。のちに舞台化、映画化され、これも大ヒット。カリフォルニアにヒッピー・コミューンを設立し、LSDを広めるアメリカ横断バス・ツアーを敢行、マルチメディア・コンサート“トリップス・フェスティヴァル”を開催するなど、60年代の若者文化、サイケデリック運動に多大な影響を与えた
岩元巌[イワモトイワオ]
1930年大分県生まれ。東京教育大学卒業。筑波大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
扉のこちら側
NAO
里愛乍
鈴