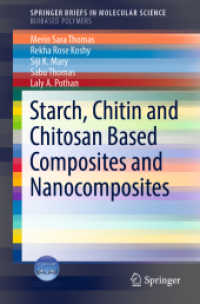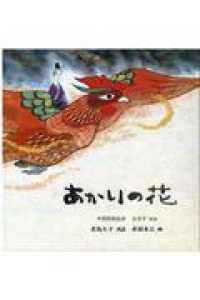出版社内容情報
ギリシア時代から育まれつづけてきた、「誰であろうが説得してしまう術」として知られるレトリック。その歴史と仕組みを、本書は具体的な事例もふんだんに、わかりやすく解説する。
内容説明
「誰であろうが説得してしまう術」として知られるレトリックとは、どのようなものか?本書は、いにしえの訴訟記録や文学作品のほか、二十世紀の政治家の弁論や宣伝広告においてのコピーなどからも具体的な事例を拾い、ギリシア時代から育まれてきたレトリックの歴史と仕組みを、わかりやすく解説する。
目次
第1章 レトリックの歴史とその仕組み(ギリシアにおけるレトリックの三つの源泉;体系としてのレトリック;衰退、復活、持続)
第2章 文彩(語の文彩―「翻訳者は裏切り者」;意味の文彩―謎と紋切り型のあいだ;構文の文彩 ほか)
第3章 論法と説得の原理(論証と証明;論法のタイプ;原理としての言い換え不能 ほか)
第4章 レトリックの哲学(レトリックの永続性―広告の戦略;レトリックと言語―「ずれ」;レトリックと誠実さ―権力 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nranjen
2
なかなか豊富で勉強になった。情報量も豊富、しっかり分類、分析、説明されている感半端ない。もう一度読みたい。2018/06/28
myung
2
ある物事を伝えるために、実際に書く、言っていることとは別の意味を喚起する表現についての本。こうして体系立てられると、なるほどすごい技術のように思われるが、実際のところ我々は意識せずとも日常的にレトリックを駆使してコミュニケーションを取っている。その確認の意味合いもあるので本書は内容の割に読みやすいと思う。特に比喩表現は、レトリックではこれでもかとばかりに細分化しているが、巷にありふれた表現ばかりだ。しかし意識するとしないとでは大きな違いがある。特に文章を書く人には有益な本になると思う。2014/12/10
はやー
1
勉強になる本。佐藤信夫の本でレトリックに興味を持ったのだけれど、この本では文学的な観点だけでなく、説得するため/論じるためのレトリック、という観点もあって面白い。2017/12/14
里馬
1
非常に読みやすく、レトリックの世界へ追いやられる。2008/05/11
きみどり
0
文彩についての第2章と、論法・論証など説得術についての第3章を中心に読んだ。第4章はよくわからないのでさーっと。小著だけど、実例がわりと多くあるのは良い。また、「レトリックによるメッセージは、反駁不能なものとして立ち現れる」という、レトリックの原理としての閉鎖性については、非常に興味深く感じた。2014/11/27
-

- 電子書籍
- わたしの中の他人【分冊】 2巻 ハーレ…