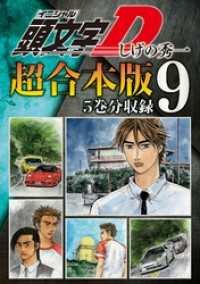出版社内容情報
ヨーロッパは暴力と混血のちぎりから生まれた。したがって多くの場合、ヨーロッパの民族をめぐる問いに答えることは、戦争と平和にかかわる。本書は、ヨーロッパ諸民族の現在(言語・宗教・慣習・食生活・領土紛争……)とその将来計画を語ることによって、民族学研究の新しい可能性を切り拓いている。
内容説明
暴力と混血の契りから生まれたヨーロッパ。ヨーロッパの民族をめぐる問いに答えることは、多くの場合、戦争と平和にかかわることだ。そのような視点からヨーロッパ諸民族の現在(言語・宗教・慣習・食生活・領土紛争…)とその将来計画を語る本書は、民族学研究の新しい可能性を切り拓いている。
目次
第1章 ヨーロッパ民族学の歴史
第2章 遺産の古層・基層・傍層
第3章 遺産の継承、同化、革新
第4章 アイデンティティの危機
第5章 好みと価値観と信仰
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
7
原著は1990年、再版1993年で、邦訳は1994年。書名通り、ヨーロッパに絞った民族についての本。ヨーロッパについて分かった気になってはいけないと思わせた一冊で、名前も知らない民族や言語がいくつも言及され、到底”欧米”なんて一括りに出来ないと再確認した。”アジア”があまりに粗雑な括りであるように。 第一章は「ヨーロッパ民族学の歴史」で、ケルト、ゲルマン、スラブというイデオロギーについて。ナチスによるゲルマン民族主義だけではないイデオロギー。→続く2021/11/28
ききょう
0
個人的には久々の学術書に緊張。忘れている用語も多かったし、要所で疑問を投げ掛けながら、その当時の最新学説をまとめあげてくれているところが、いま再び最新学説を知りたいと望む私にはありがたかったです。 基本に立ち返えれました。 備忘録。民族学の基礎の3つの学問的伝統は以下。 ・社会学 ・文献学、言語学、民俗学 ・文化人類学、社会民俗学 政治機構は社会学、宗教は民俗学にもに入りますが、それぞれ、独立した学問でもあるし、地理学も考古学も史学も関係する…やっぱり私はこの学問に助けられて仕事して来たんだなぁ…2014/10/30
メコノプシスホリデュラ
0
ヨーロッパの民族を「言語使用、領土所有、慣習的行動や宗教儀礼を意味づける将来計画や行動」などでアイデンティティを保つ民族性から分析、グループ分けし、また社会の中で民族的アイデンティティが保たれ形成されるメカニズムを記述する。まずヨーロッパの古層をサーメ人(ラップ人)、バスク人に、より新しい基層としてインド・ヨーロッパ祖語(話者はカルパチア山脈、コーカサス地方、ウラル山脈にはさまれた地のクルガン人)を共通祖語とする民族、傍層としてフィン・ウゴル系(フィンランド、エストニア、ハンガリーなど)トルコ系に分ける。2014/02/28
KBS
0
このへんに書かれてることをつなげられるようになりたい2012/08/29