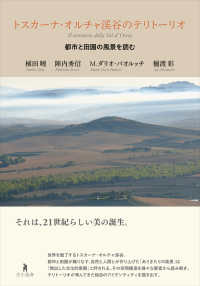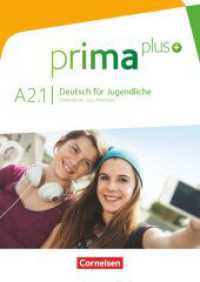出版社内容情報
異端審問という言葉ほど、恐怖に満ちた語はない。ヨーロッパおよび新大陸における宗教裁判はいまだ我々に恐怖心を起こさせる。本書は、その実体、その成立と消滅の過程、裁判の実際、各国での状況などを十二世紀から第二ヴァチカン公会議まで、逸話を交えて紹介する。特にスペイン、南米での記述に詳しい。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
k5
59
積読本の深い地層から発掘。たぶん院生の頃に買ったから、ドストエフスキーの「大審問官」とかの連想だったのですけど、西洋史ヲタ化している現在に読んでよかった。すごく充実した内容で、異端審問の実際について、それこそ手続きや審議の進め方まで書いてあります。巷間イメージされるような火焙りや拷問は宗教裁判の中ではあまり用いられず、世俗の裁判所の方が残酷だったなど発見もあります。地域的にもヨーロッパだけでなくラテンアメリカもカバーしており、短い本ですが、本当に充実した内容でした。2021/09/11
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
4
第一章。異端審問所の起源は十二世紀末の教皇令だった。異端審問は世俗権力の協力が必ずしも得られないために、教皇直属の軍隊が必要で、それが托鉢修道会だった。それも地方の司教との対立をもたらした。 第二章。異端審問所はイギリス以外の全ヨーロッパに設立されることとなった。イギリスでは異端が排除されていたからだ。その異端の勢力は時に教皇を追い出すほどであった。第三章。異端審問の手口。詳細は書ききれないが、おおよそ想像通り。さすがに遺体を掘り返して市中引き回しの上で焼却するというのは知らなかった。→続く2021/03/18
わかや
1
異端審問所の行う宗教裁判は残酷じゃないというのが意外だったが、世俗裁判所や民衆の行う裁判や魔女狩りの陰惨なイメージと混同していたのかもしれない。2011/11/17