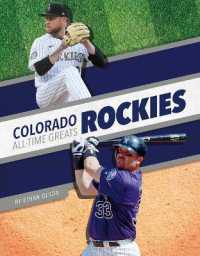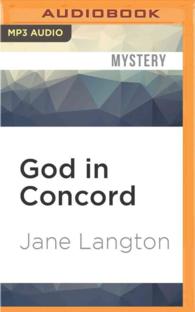出版社内容情報
古来、聡明な頭脳は失言を愛した。19世紀初頭、ドイツはゴータの町の高校で教鞭をとったガレッティ先生の膨大な失言は、我々の哄笑を誘いながらも、先生の温かい人間味を感じさせずにはいない。一例を挙げよう。「この個所は誰にも訳せない。ではいまから先生がお手本をお見せしよう」。
内容説明
ドイツのプロフェッサーが残した前代未聞、抱腹絶倒の名「失」言。歴史・地理・天文学・博物学・人類学・文学…。これは人類の知のありとあらゆる分野における壮大なナンセンスの宝庫である。
目次
古代の世界
歴史学
自然地理、ならびに政治地誌学
天文学と物理学
数学、幾何学、算術
年代記
博物学
人類学
言語学と文学
授業風景
私事
経験と省察
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
がんつん
5
これは愛すべき語録。まさかの失言語録です。おかしみにあふれた、すてきな本ですぞ。自分もやりましたねー。授業中の先生が言った名言やら口癖をメモったりカウントしたり。かくいう私もなぜかクラスメイトに語録を作られていたのですが(笑)2014/06/13
蕃茄(バンカ)
3
失言録というジャンルの本があることを知らなかったが、読んでみるとニヤニヤを抑えることができない。意味不明な発言から実は深い意味があるのではと思わせる発言まで様々だが、こうしたおかしな授業で親しまれている先生は自分の身近にも確かにいた!200年ほど前から変わらない学校の光景というのはあるのだなと思うと感慨深い…こともない。2015/02/10
夕立改二
3
この本で読んだことはすべて頭の中から叩き出さなければならない。荒唐無稽、矛盾、トートロジー。筋も理屈もまったく通らない。歴史上の人物たちは産まれた年よりもずっと前の年に死ぬ。死去した後に処刑され二度死ぬ者もたくさんいた。地理歴史も自国ドイツについての発言は辛うじて100%の誤りになることを免れているものもあるが、これがアラブやアフリカ、アジアになると庇いだてのしようもなくなる。動物・植物・鉱物の区別はきわめて曖昧である。しかしガレッティ先生はこう言う――「教師はつねに正しい。たとえまちがっているときも」。2014/04/08
ワッピー
3
大部の学術書をものしたにもかかわらず、今ガレッティ先生の名を高めているのはこの失言録。「いいまつがい」の原因は主語・述語のねじれ、数の不一致、カテゴリの混乱などいろいろ考えられるけれど、たまに命題的に真であるものとか、妙に哲学的な言葉も混ざっていたりする。この先生の講義は人気だったんだろうね。文脈から一節だけを切り離したら誰でも失言なんていくらでもあるでしょうと思ったけど、「ドイツでは、毎年、人口1人あたり22人が死ぬ」って、あなた・・2013/06/08
真塚なつき(マンガ以外)
3
再読、初めて読んだのはもう十年以上前になるか。タイトルから何か含蓄の深い話を期待するならお生憎様、これはたんなる言い間違い、ガレッティ先生の失言を教室の悪たれ小僧どもがノートの端に書き残したもの。失言録とはいうものの「水は沸騰すると気体になる。凍ると立体になる。」などは洒脱だし、「教師はつねに正しい。たとえまちがっているときも」には生徒への叱責のようでもありながら、しかし鋭い風刺もただよっており、博覧強記のひとガレッティ先生の知性を感じさせる。現代日本で似たものとしては糸井重里の『言いまつがい』がある。2012/12/01