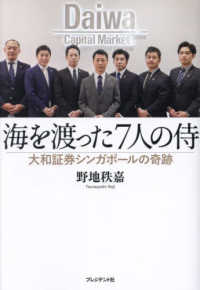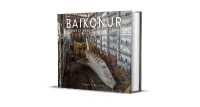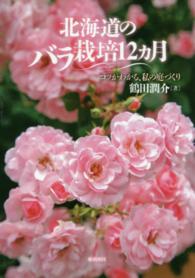出版社内容情報
小澤征爾をはじめ、世界的な演奏家を数多く育てた、たぐいまれな教育者が、音楽芸術全体にわたって明快に語る唯一の講義録。音楽を愛し演奏するすべての人々に贈る珠玉のメッセージ。
内容説明
1972年~1974年、桐朋学園大学音楽部附属子供のための音楽教室広島分室における講義の記録。音楽を愛し演奏するすべての人々に贈るたぐいまれな教育者の珠玉の言葉。
目次
第1回 音楽芸術とは(序論―バッハからロマン派へ;バッハとその解釈について)
第2回 メロディーについて(メロディーと言葉;メロディーの発生と進歩)
第3回 音楽の構造を考える(対照が構造をつくる;メロディーの構成について)
第4回 リズムとテンポ(機械的なリズムと有機的なリズム;音楽と心)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろみ
12
小澤征爾さんが亡くなって、YouTubeのおすすめが関連動画でいっぱいになりました。4回に分けて最後は亡くなる前月の講義録。テープから起こしてお話しされたまま書かれているので、より内容が身近に感じられます。譜例がたくさん掲載され、講義はご本人やお弟子さんが弾きながら行われたそうです。「譜面の通り演奏すれば、本当につまらないものが出来る」こうやって描かれた山を見ながら、練習がんばろーう。2024/03/10
ゆうちゃん
2
日本いや世界のクラシック音楽の発展に多大な貢献を教育をもって成された斎藤秀雄さんの講義録。誰もおそらく閃かないであろうことを軽々と言っておられたり、本質をつく知恵を的確な例えを用いて理解しやすいよう変換して解説されたり、このような人が戦後日本にいたのかと、驚愕と尊敬を持ちながら読み進めた。本書に出会えて大変良かったと感じる。2015/12/27
敬之
2
非常に得るところ多かった。 必然を作る ニュアンスと強弱の違い 芸術は錯覚を利用するもの など2013/04/06
ユミセツカヤ
1
日本人が西洋音楽に惹かれ、理解しようとする道筋に触れられた。話言葉なので、理解が難しいところもあったけれど、膨大な知識に基づいた講義は、すばらしいと思った。「審美眼」を自分で育てる、そのための知識は必要で、それはもう無限なんだな、と感じた。 面白かったのは、ピアニストのケンプに対する口述。私も同じように感じていたので、親しみを感じた。2016/05/31
Yakmy
1
桐朋を作り上げて、小澤征爾をはじめ、日本を代表する音楽家を育て上げた齋藤秀雄が、「桐朋子どものための音楽教室」の広島分室を立ち上げたときに広島で行った講義をまとめている。齋藤の音楽に対する厳しさがよく見えてくる。 特に何度も言っていたのは、音楽の構造を捉えることの大切さだ。構造を理解しないことには、音楽のおもしろさは生まれない。そして、構造とは対照から生まれるともの繰り返し述べている。「大きい-小さい」「速い-遅い」といった対照から、音楽のドラマが生み出されていく。2015/06/24
-
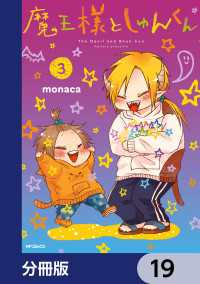
- 電子書籍
- 魔王様としゅんくん【分冊版】 19 M…