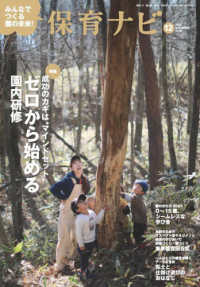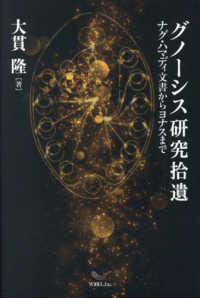出版社内容情報
死海写本とともに今世紀最大の考古学上の発見といわれ、キリスト教の基本概念を揺さぶるものとの反響を呼びながら、その全貌が知られていなかった古代文書について、その発見から本文公刊に至るまでの劇的経過を明らかにするとともに、今日のキリスト教を大胆に問い直す、注目の論考。
内容説明
死海写本と併せて、今世紀最大の考古学上の成果といわれる本写本の発見経過とその意義を、気鋭の女流学者が劇的に解明する。
目次
第1章 キリストの復活に関する論争―史実か象徴か
第2章 「唯一の神、唯一の司教」―唯一神教の政策
第3章 父なる神、母なる神
第4章 キリストの受難とキリスト教徒の迫害
第5章 どの教会が「真の教会」か
第6章 グノーシス―神認識としての自己認識
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
34
21
二つの惑星がぶつかって片方は気づけば他方の衛星となっていた。正統とは、異端との衝突によって修正されたこの質料のことである。この本を読んで考え直すよう促されたのは、異端の思想に照らされた正統の教義がいかに逆説に充ちて見えるかということ。処女懐胎、受肉、復活。信じられた逆説は強制力をもつ。神学とはこの逆説の解釈学のことだが、最初の神学者はグノーシスの徒だった。彼らはこの逆説をヘレニズム的に解釈し、彼らと抗争することでキリスト教ははじめてその真の姿に(すなわち脱ヘレニズム化に)達したようである。2019/03/01
スズコ(梵我一如、一なる生命)
15
ナグ・ハマディ文書の考古学的側面を知れればと思って手に取ったが、正統派キリスト教が組織的・神学的体系の整備により競争に勝つに至ったのに対し、グノーシス派がキリスト教をどう捉え、どう考える性質だった故に異端として迫害され、また(争いという観点から)そうならざるを得ない性質だったのかが解かれていた。難しい点も多かったけれど、なかなか刺激的で面白かった。グノーシス派と正統派はタイプの違う人間に対し訴えるものである、ってのに納得。だからこそ、グノーシス的視点、在り方は消えることない→2024/05/12
レートー・タト
1
第三十一回全米図書賞、宗教・精神世界部門受賞(1980)。本来のタイトル名の直訳は『グノーシス諸福音書』。ペイゲルスは、大まかに言って、キリスト教成立史における正統派を称するキリスト教会の確立と、異端と目されたグノーシス諸派(キリスト教的グノーシス主義)の関わりを、1945年に発掘されたナグ・ハマディ文書を資料として交えて再構築しようと試みている。イエスの権威とその受肉・復活に関する論争(史実か象徴か)、ジェンダー問題を絡めた人間論など、若干フェミニズム的傾向があるが、刺激的な考察がなされている。2010/11/21
ウハタ
0
写本丸っと載ってる訳ではなく、それが書かれた時代、キリスト教初期時代の正統派とグノーシス派についての一冊。ユダの福音書を読んで疑問に思った事を知りたくて読んだけど答えに当たるモノは無し。正統派とグノーシス派は色々な面で対照的で共通する部分も有り。お互い傲慢だって批判してるけど言われる理由は解る。文章が難しく何言ってんだか理解出来無い文がちょいちょいあったのでもう一回読んでみる。対比してあるので解りやすい部分も有ったけどグノーシス派の教えにもっと詳しい本が読みたい。2021/02/02
-
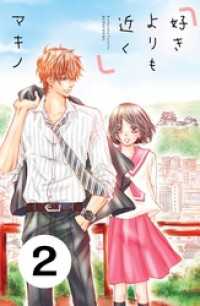
- 電子書籍
- 好きよりも近く 分冊版(2)