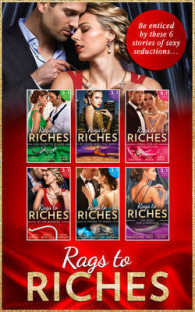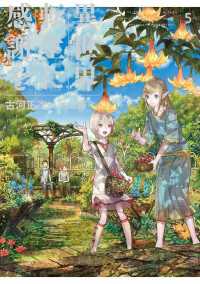内容説明
かつて本は鎖で本棚につながれていた!巻物から写本、そして印刷術の発明―そんな書物の発達とともに歩んだ収納法の進化の跡を名著『鉛筆と人間』の著者がたどる。読書人・書店・図書館関係者必読の好著。
目次
第1章 本棚の本
第2章 巻物から冊子へ
第3章 保管箱、回廊、個人用閲覧席
第4章 鎖で机につながれて
第5章 書棚
第6章 書斎の詳細
第7章 壁を背にして
第8章 本と本屋
第9章 書庫の工学
第10章 可動書架
第11章 本の取り扱い
著者等紹介
ペトロスキー,ヘンリー[ペトロスキー,ヘンリー][Petroski,Henry]
デューク大学土木環境工学・建築土木史教授
池田栄一[イケダエイイチ]
1951年生。九州大学大学院修士課程修了。英文学専攻。東京学芸大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
28
★★★★☆ 16世紀まで本は鎖に繋がれていた、鎖に繋がれていたため、本は現在のような背表紙を前にして本棚に入れるのではなく、背表紙を後ろに向けて入れていた、しかし、活版印刷術が発達し、本の希少価値が薄れてくると、鎖で繋ぐ必要はなくなり、さらに、本の数が膨大になると横にして入れると数が入らないので今のような縦に入れるやり方になったという2016/08/06
猫
4
図書館本。本と本棚の複雑な関係とその移り変わりを追う。本の形態の変化やその価値に合わせて、保管方法や適した形を追求して変化してきた本棚。本が存在する限りその存在は必須で必ずそこにあるのに、目の前に立つに人の目は本を見て本棚はほぼ確実に見ていない。という指摘に、確かに図書館の本棚がどんな造りか思い出せないことに気づかされた。2020/06/21
hutaketa
4
これを読まずして愛書狂は名乗れない。本と本棚の歴史を通して、図書館や読書のマナー、収納・保管について知ることができる一冊。電子書籍云々と言い出す前に、本の過去について勉強するのも悪くない。2010/10/22
iwtn_
3
本棚本。原題に合わせて「本棚の本」とかにしたほうがキャッチーだとは思ったが、主に西洋の本を収める器具や設備についての歴史を書いているので、間違っているわけではない。著者のファンだし、本棚を最近一つ増やしたところだったので(そしてこの本もその本棚に入ることになる)興味深く読めた。工学的な観点からも色々と勉強になる内容で、コンピュータが出る前の「IT」の話でもある。一部未来の書籍がどうなるかを検討している部分があるが、流石に予想通りとはいかなかった様子。しかし電子書籍も権利という鎖で繋がれているわけだ。2024/08/31
takao
1
本の形態が本棚の形を規定2024/10/08