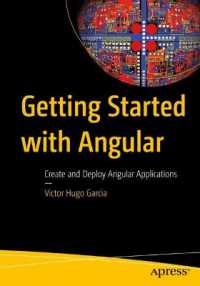出版社内容情報
全国民が飢餓線上をさ迷っていた時代から、米増産の華々しい成果を上げた時代までの、米価政策と米価運動。高度経済成長を支えた農民の経済力を生み出した米価はいかに決定されたか。
目次
敗戦直後の米穀政策―1945~48年(飢餓線上にあった食糧事情と悪性インフレの進行;米麦等の供出確保対策;集荷・配給制度の改正;物価安定のテコとされた低米価の決定;標準売渡価格、消費者米価の決定事情)
食糧事情回復期の米穀政策―1949~51年(米の追加供出の法制化;食糧事情の回復と米麦の統制撤廃論の浮上;供出の事後割当と配給業務の民営化;米価審議会の発足と生産費による米価要求;食管会計収支均衡主義による消費者米価の決定)
供出制度行詰り下の米穀政策―1952~54年(麦の統制撤廃と売渡申込にもとづく無制限買入れ;米供出制度の行詰りと集荷対策;割当方式から自主的売渡申込制への切替対策;複雑になった生産者米価体系;家計米価方式導入による消費者米価の決定)
新農政展開下の米穀政策―1955~59年(経済の拡大と新農政の展開;予約売渡制の発足;食管制度検討の調査会相次いで設置;米の順調な集荷と希望配給・キロ建配給制の実施;引下げまたは据置きとなった生産者米価;財政負担縮小のための消費者米価の改定)
高度経済成長下の米穀政策―1960~67年(高度経済成長と農業基本法下の農政;米需給事情の変転;河野農相の米自由販売構想とその結末;米の集荷と配給;農協の米価運動の進展;生産費及び所得補償方式に基づく生産者米価の決定;指数化方式による生産者米価の決定;積上げ計算方式への転換;消費者米価の改定)