出版社内容情報
25年間の歴史を持つ中山間地域等直接支払制度が揺れている。直接の契機は、本制度の5期対策(2020~2024年)に導入された集落機能強化加算について、農水省が廃止を打ち出したことにある。本書は2000年度から発足し、「集落協定」という農村集落を基盤とする日本独自の支援方式として設立、展開してきた制度を、農村社会の変化とあわせて振り返る。第5期末のおける混迷の要因を冷静に分析しつつ、今後のあり方を展望する、それは農村政策の問題であると同時に、制度設計における透明性の確保という課題に答えることでもある。
【目次】
第1部 原点
1章 制度形成の背景と特徴
1 中山間地域問題の概観─問題の展開
2 中山間地域政策の展開とその特徴
3 新基本法下の中山間地域対策の方向と特徴─「日本型」直接支払政策
4 中山間地域政策の課題─直接支払政策の導入下において
2章 地域における第1期対策の成果と課題
1 直接支払制度の特徴
2 制度導入初年度における実施状況
3 集落協定締結へ向けた諸対応
4 協定締結を契機とする地域的活動の実態
5 直接支払制度の課題
◎補足 集落協定の知恵袋
3章 評価と課題
1 はじめに
2 直接支払い制度の実施状況―2年間の概況
3 制度の目的と政策評価の視点
4 直接支払制度による農業・農村の到達点
5 直接支払い制度の課題―第2期対策に向けて
第2部 展開
4章 制度の変遷と性格変化-第2期対策から第4期対策
1 はじめに
2 中山間直払制度の仕組みと実績
3 「集落協定」の枠組みと実態?内発的発展促進的性格
4 制度の変化と内発的発展促進的性格の動揺
5 地域の対応と教訓
6 おわりに-中山間直払制度のあり方の展望
第3部 迷走
5章 混迷の本質―第5期対策から第6期対策
1 はじめに-混乱の概況
2 第5期の特徴-集落戦略と加算措置
3 集落機能強化加算廃止をめぐる経過と問題
4 第6期対策の特徴?集落戦略からネットワーク化活動計画へ
5 第5期対策と第6期対策の相違?「混乱」の真因
◎補足 集落機能強化加算の第6期への経過措置
第4部 展望
6章 地域と制度の四半世紀―未来へ
1 地域の四半世紀
2 協定の内実変化と制度の変遷
3 制度の変化と成果
4 制度をめぐる四半世期?小括
5 制度再生の論点-教訓からの提言
6 おわりに-混乱を教訓にオープンな議論を
◎資料 中山間地域フォーラム・緊急声明
内容説明
25年の歴史をもつ中山間地域等直接支払制度が揺れている。その直接の契機は第5期対策(2020~2024年度)に導入された集落機能強化加算について、農水省が次期対策における廃止を突然打ち出したことにある。2000年度に発足した中山間直払制度は、「集落協定」という農村集落を基盤とする支援方式として制度設計された。EU農政の条件不利地域支払いとはまったく異なる、独自の「日本型直接支払制度」であった。本書は5期25年にわたる制度の原点、展開を振り返ったうえで、今回の混迷の真因を冷静に分析し、農村社会の変化を踏まえつつ制度のあり方を展望する。ひとつの制度にとどまらず農村政策や直接支払いなど財政負担型制度の方途にも言及し、さらに農政全般における政策形成のあり方を問題提起する。
目次
第1部 原点(制度形成の背景と特徴;地域における第1期対策の成果;評価と課題)
第2部 展開(制度の変遷と性格変化―第2期対策から第4期対策)
第3部 迷走(混迷の本質―第5期対策から第6期対策)
第4部 展望(地域と制度の四半世紀―未来へ)
著者等紹介
小田切徳美[オダギリトクミ]
明治大学農学部教授。専門は農政学・農村政策論、地域ガバナンス論。1959年、神奈川県生まれ。東京大学大学院農学系研究科博士課程単位取得退学。博士(農学)。農林水産省「中山間地域等直接支払制度検討会」委員。「中山間地域等総合対策検討会」(第1期、第2期第三者機関)委員
橋口卓也[ハシグチタクヤ]
明治大学農学部教授。専門は農業経済学、農政学。1968年、鹿児島県生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了。博士(農学)。農林水産省「中山間地域等直接支払制度に関する第三者委員会(第5期)」委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
-
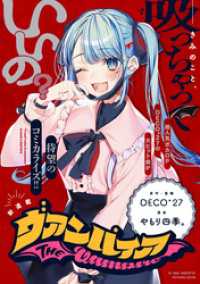
- 電子書籍
- ヴァンパイア 【連載版】: 9 HOW…
-

- 電子書籍
- 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~【…







