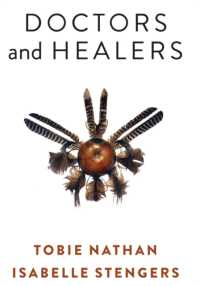出版社内容情報
本書は酪農通史である「第一編 日本酪農の近現代--牛乳を通して学ぶ歴史構造」と、100年企業を含む6つの地域乳業への聞き取り「第二編 地域乳業の生命力--地域の事例から学ぶ産業史」から構成されている。
ウクライナ戦争を契機とした食糧危機をはじめ、現在、日本の酪農産業は未来への危機意識や閉塞感が高まっている。その中にあって酪農産業の「生命力」とはなにか? 答えの鍵は日本の牛乳市場の8割を占める「地域乳業」の中にある。6企業の事例研究と、日本の酪農通史から、持続可能な未来への新しいカタチを探究する。
【目次】
内容説明
岐路に立つ日本酪農の「ダイナミクス(生命力)」とはなにか?その答えの鍵は、牛乳市場の8割を占める「地域乳業」の中にある。酪農という産業の史的構造から、未来へと向かう持続可能な成長理論を展望する書。
目次
第一編 日本酪農産業の近現代―牛乳を通して学ぶ歴史構造(近代酪農産業の前史とその文化的な性格;明治期―牛乳搾取業の誕生と展開;大正・昭和戦前期―農民的酪農の登場;戦前戦後―有畜農業政策と酪農の展開;製糖・製菓資本の市場参入と大手乳業の誕生;戦後における酪農産業の急速な発展;小売業の流通革命から現在に至るまで;わが国酪農産業の時代区分とその特徴)
第二編 地域乳業の生命力―地域の事例から学ぶ産業史(牛乳流通構造の変遷;地域乳業経営の歴史構造―事例1「YUDAミルク株式会社」;地域乳業経営の歴史構造―事例2「トモヱ乳業株式会社」;地域乳業経営の歴史構造―事例3「新潟県農協乳業株式会社」;地域乳業経営の歴史構造―事例4「中央製乳株式会社」;地域乳業経営の歴史構造―事例5「ひまわり乳業株式会社」;地域乳業経営の歴史構造―事例6「永利牛乳株式会社」;地域乳業の成長理論へのアプローチ)
著者等紹介
前田浩史[マエダヒロフミ]
1955年宮崎県生まれ。宮崎大学農学部卒業後、社団法人中央酪農会議、一般社団法人Jミルクなどの酪農乳業団体に40年余り在職。元・一般社団法人Jミルク専務理事。現在は、「ミルク一万年の会」代表世話人、「乳の学術連合・乳の社会文化ネットワーク」幹事、「日本酪農乳業史研究会」常務理事など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- FLASHデジタル写真集 白濱美兎 僕…
-
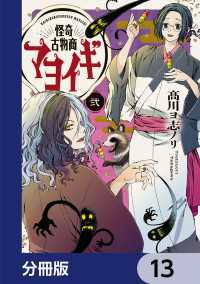
- 電子書籍
- 怪奇古物商マヨイギ【分冊版】 13 電…