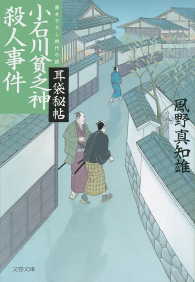出版社内容情報
本書のキーワードは「すき間」である。「すき間」とはなにか。それは、農学が提案するあるべき農法と風土が求める農法の「すき間」である。筆者は奈良盆地の農業を大和農法と名付けた。それを支える農学的根拠は、大和農学とでもいうべきものである。山形県の庄内農法では庄内農学のように。つまり、各地の風土農法には、対応する各地の風土農学がある。本書で明らかにするのは、これである。
第1章は、前史である。明治期からの農法論研究を丹念に見ていく。日本の農学はおもにドイツ農学の影響を受けており、「大きなすき間」があった。第2章では、加用信文を検討する。戦後農業の混迷期に、世界史の発展法則としての段階論的農法論を唱えて、西ヨーロッパをモデルとする一つの発展方向を明示した。しかし、そこには「大きなすき間」があった。加用は苦悩し格闘して、生態的農法論へと理論的に転換した。風土農学が受け継ぐべき提案であった。
第3章は、飯沼二郎である。高度経済成長のもとで、加用のモデルを批判してそこから脱却するアジア・日本農法を、風土を導入した地域類型論的農法論による農業革命論の検討を通じて提案した。風土論により「大きなすき間」は小さくなったが、静態的という限界があった。いかに風土論を動態化させるかを提案する。
第4章は、熊代幸雄による、加用の発展段階論と飯沼の地域類型論を統一しようとする比較農法論を検討する。「生命意識」「生命倫理」は、風土農学にとって貴重な視点となろう。
第5章は、筆者が長年検討してきた守田志郎である。基本法農政の破綻・減反を批判する『農業は農業である』を71年に刊行して、加用・飯沼・熊代の戦後農法論をちゃぶ台返ししてしまう。「すき間」が自覚化され西欧モデルは否定された。守田の実像を明らかにし、生産と生活が結びついた守田農法論を発展させて、風土農学へと繋げていくことをめざしている。
第6章では、椎名重明や石川三四郎を検討する。第7章では、農法論と現場の農法・農学との「すき間」を埋める努力が、日本列島内ではなく戦前の外地での農学研究でなされていたことを紹介する。
第8章では、八世紀の古風土記を検討し、それらがその後にどのように受容され展開していったのかを検討する。続いて古風土記を再興する江戸時代の地誌を紹介し、風土農学を江戸農書に探ってみる。続いて、小野武夫と黒正巖を紹介する。第9章では、明治期に著わされた牧口常三郎の『人生地理学』をとりあげる。今まで農学研究では全く検討されてこなかったが、風土農学を考えるうえでは欠かせない研究である。
最後の第10章では、こうした提案の学説史的な意味を、もう一度農学史の検討から確認する。明治期の現場の「経験」と農学士たちの「学理」はどのように農学として融け合ったのか。現場の農業者の「自負」の行方はどうなったのか。江戸農書は自前の農学ではなかったのか。そして最後に、風土農学を流れる自然観の変遷を追いながら、中国・インド・ヨーロッパからの外来思想とどのように融け合ってきたかを検討する。
【目次】
はじめに 創発する風土から農学をとらえなおす
第1章 欧米農学の直輸入」から「日本」の発見
第1節 明治期から戦前までの農法論
第2節 久保佐土美・青鹿四郎の活躍
コラム1 久保佐土美の歩み
第2章 加用信文の農法論における生態論への転換――戦後農業の混迷に、西欧をモデルとする一つの発展方向を明示
第1節 世界史の発展法則としての段階論的農法論
第2節 加用の生態論への理論的転換を活かす
第3章 飯沼二郎の農法論における風土の限界――高度経済成長のもとで、西欧モデルから脱却するアジア・日本農法の提案
第1節 地域類型論的農法論からの農業革命論
コラム2 飯沼先生に導かれて
第2節 静態的な飯沼風土論を動態化させる
第4章 熊代幸雄の農法論における生命論の意義――日・中・欧の比較農書論からグローバルに考える
第1節 段階と類型を統一する比較農法論
コラム3 棚橋初太郎、熊代と会う
第2節 生命意識による熊代農法論を受け継ぐ
第5章 守田志郎の農法論における生活的循環論の展開――基本法農政の破綻・減反を批判する「農業は農業である」
第1節 戦後農法論のちゃぶ台返しと西欧モデルの否定
コラム4 守田の愛読書:ハワード『農業聖典』
第2節 守田の虚像と実像、守田農法論を発展させる
第6章 椎名重明の農学思想論における「自然愛」への飛躍
第1節 『農学の思想』におけるマルクスの否定
第2節 クロポトキンの相互扶助論への共感
コラム5 宮本常一のクロポトキン
第7章 外から日本列島の農学をとらえなおす
第1節 中国・北京農村経済研究所からのまなざし
コラム6 渡辺兵力の華北農村調査
第2節 朝鮮農業試験場からのまなざし
第8章 創発する「風土」を発見する旅(Ⅰ)
第1節 古風土記から江戸農書へ
第2節 小野武夫と黒正巌
コラム7 小野武夫の原点
コラム8 黒正の飯沼二郎への「注意」
第9章 創発する「風土」を発見する旅(Ⅱ)
第1節 牧口常三郎『人生地理学』から黒澤酉蔵『農業国デンマーク』へ
コラム9 牧口と三澤の出会い?
第2節 二〇世紀から二一世紀の風土研究
第3節 三澤の「風土」から二一世紀の「創発する風土」へ
第10章 「自前の農学」としての風土農学
第1節 明治期の「経験」と「学理」
第2節 江戸農書は「自前の農学」
第3節 風土農学に流れる自然観の変遷
コラム10 アフリカからのまなざし
おわりに 日本列島の風土農学は「おかげさま・おたがいさま」の世界
あとがき
内容説明
「風土」と聞けば、何かしら古くさいイメージを持つかもしれない。そう、古い。だからいいのである。和辻哲郎やベルクとは一味違う。日本列島に息づいてきた農業者たちの汗と涙と喜びに共存する風土論。守田志郎や石川三四郎など先人たちは、農業者たちとの「すき間」を埋めようと格闘した。各地の「風土農法」には、対応する各地の「風土農学」がある。本書が明らかにするのはそのことである。
目次
第1章 欧米農学の直輸入から「日本」の発見
第2章 加用信文の農法論における生態学への転換 戦後農業の混迷に、西欧をモデルとする一つの発展方向を明示
第3章 飯沼二郎の農法論における風土論の限界… 高度経済成長のもとで、西欧モデルから脱却するアジア・日本農法の提案
第4章 熊代幸雄の農法論における生命論の意義 日・中・欧の比較農書論からグローバルに考える
第5章 守田志郎の農法論における生活的循環論の展開 基本法農政の破綻・減反を批判する「農業は農業である」
第6章 椎名重明の農学思想論における「自然愛」への飛躍
第7章 外から日本列島の農学をとらえなおす
第8章 「創発する風土」を発見する旅1
第9章 「創発する風土」を発見する旅2
第10章 「自前の農学」としての風土農学
著者等紹介
徳永光俊[トクナガミツトシ]
1952年 愛媛県松山市に生まれる。2010~2019年 大阪経済大学 学長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。