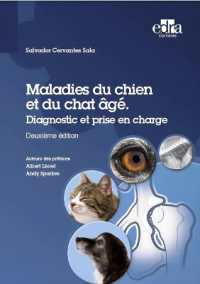出版社内容情報
本書は、作物・微生物・土壌から見た第1・2章、農業者から見た第3・4章、そして広く歴史・社会から見た第5・6章と、三部構成となっている。
「第1章 根本原理としての生きもの循環」では、「忌地」と呼ばれる連作障害を取り上げ、「忌地」をめぐる農業者、作物、土壌・微生物という三者の生きものたちの関係を探る。「第2章 風土が響存する生きもの循環」は、作物=光合成生産者、農業者と動物=運搬者、微生物=土壌形成者の三者が「生きもの循環」を形成してきたことを説く。
「第3章 狭義の農法=農術における内的発達法則」は本書の核心にあたる。最初に奈良盆地の水稲反収の推移から、大和農法五〇〇年の小・大・超S字カーブを発見しそれを説明する。次に「第4章 変容する農術の開発・普及・定着過程」では、農術の展開に農業者がどのような役割を果たしたかを、大和農法を事例に考える。
「第5章 作付け方式からみる風土農法の流れとかたち」では、山形県・日本海側の庄内農法における水稲反収の推移を検討する。さらには連年の時間的な作付順序と一年での空間的な作付割合を組み合わせた「作付方式」の推移を、全国的かつ歴史的に検討する。
「第6章 農術から広義・大義の風土農法へ」では、奈良盆地の大和農法を念頭に置きながら、狩猟採集から半栽培や畑作、稲作が始まり普及していく時期を「天然農法」、稲作が伝来して作付が始まり、国家によって強制されていく6、7世紀頃よりを「人工農法Ⅰ」、13、14世紀頃より商業的農業が展開していく時期を「人工農法Ⅱ」、1960年代より機械化・化学化・施設化が進む時期を「人工農法Ⅲ」とする。そして21世紀に創造されていく風土農法を「天工農法」と名付ける。
現在行われている有機農業や自然農法は、反・人工農法Ⅲ、そしてもっと長期的にみれば反・人工農法として位置づけられる。今後は、有機農業や自然農法を組み込んだ、AIやロボットなどのスマート農業も活用する、「生きもの循環」に則った「天工農法」が、農家自身によって開発されやがて多数農民によって受容されていくのではないかとする。どちらかではなく、両者の融合である。
生きもの循環の基本原理は、日本列島で代々伝えられてきた「おかげさま・おたがいさま」「いただきます・ごちそうさま」という日常生活の和語の世界。本書では、三澤勝衛の風土産業論、作物風土論を軸に、風土農法論を展開し、今では忘れかけられている「おかげさま・おたがいさま(+いただきます・ごちそうさま)」の世界を、21世紀において天工農法により再興することを目指している。
内容説明
本書は日本列島の農法史の歩みを歴史的事実に即してふり返りながら「生きもの循環」「風土」「農法」をキーワードにしてとらえなおしてみようとするものである。アグロ・エコロジー、最近ではサステナブルではなくリジェネラティブなどがもてはやされる。こうした見方は、実は日本列島の「風土農法」において、早くから生まれていた。「まわし・ならし・合わせ」の江戸農書、「直耕」の思想家・安藤昌益、信州諏訪の「風土産業論」の三澤勝衛、『風土と環境』の作物学・栗原浩など…。その水脈は現在まで滔々と流れ続けている。風土とともにある農法再考の書。
目次
第1章 根本原理としての生きもの循環
第2章 風土が響存する生きものの循環
第3章 狭義の農法=農術における内的発達法則
第4章 変容する農術の開発・普及・定着過程
第5章 日本列島における風土農法の流れとかたち
第6章 農術から広義・大義の風土農法へ
著者等紹介
徳永光俊[トクナガミツトシ]
1952年愛媛県松山市に生まれる。2010~2019年大阪経済大学 学長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
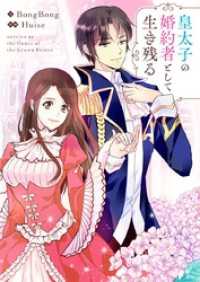
- 電子書籍
- 皇太子の婚約者として生き残る【タテヨミ…