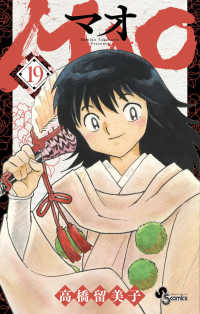出版社内容情報
1973年刊行の名著が読みやすくなって復活!現在の稲作基本技術となったV字型理論の決定版。への字、太茎大穂の理解にも重要。
内容説明
早期茎数確保、中期にデンプン蓄積を高めるV字型稲作理論は、現在の稲作技術の原点。V字型稲作を批判するへの字型理論、太茎大穂型理論を理解する上でも重要。
目次
第1章 収量構成のしくみと増収のねらいどころ(なにを目標に増収を考えるか;穂数はこうして決まる ほか)
第2章 簡単にできるイナ作診断(イナ作改善はまず成熟期の診断から;モミ数と登熟歩合と収量との関係 ほか)
第3章 安定多収栽培の実際―診断結果の応用(発育段階に合わせた栽培;計画的なイナ作 ほか)
第4章 理想イネによる多収・安全・良質イナ作(なぜ多収はむずかしいか;いつチッソがきくと登熟歩合は低下するか ほか)
第5章 株まきポットイナ作と多収穫栽培(株まきポット考案の動機;株まきポットの考案 ほか)
著者等紹介
松島省三[マツシマセイゾウ]
明治45年長野県に生まれる。昭和9年東京大学農学部農学実科卒業。農林省農事試験場鴻巣試験地(昭9~10年)、農林省九州農試(昭10~13年)、島根県農試(昭13~19年)、山口県農試(昭19~23年)、農林省農事試験場技術部(昭23~25年)、農林省農業技術研究所物理統計部(鴻巣分室、昭25~35年)、国連食糧農業機構(FAO、昭35~37年)、農林省農業技術研究所物理統計部調査科長(昭37~45年)、同物理統計部長(昭45~48年)を経て昭和48年退官。日本工営株式会社技術顧問に就任。農学博士。平成9年3月、85歳で逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- ガラスの心を抱いて【分冊】 3巻 ハー…
-
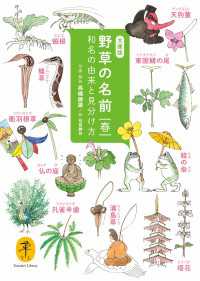
- 電子書籍
- ヤマケイ文庫 野草の名前 春 山と溪谷社