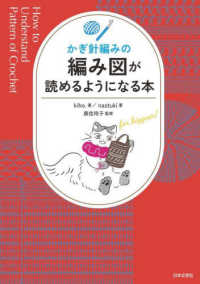内容説明
ヨーロッパ近現代の経済思想家たちは貨幣をどのようにとらえてきたか。なぜ彼らは「貨幣をめぐるジレンマ」を克服できなかったか。そこから、経済を社会に埋め戻す道を考える。著作集収録にあたりカール・ポランニーとシルビオ・ゲゼルにかかわる補章を書き下ろし。ほかに「古典経済学の思想史から見える『お金』の不思議」など三編を収録。
目次
貨幣の思想史(プロローグ 人間と貨幣の関係;国家の富の創出―ウィリアム・ペティと『政治算術』 ほか)
労働という習慣を考える
「時間」が管理する時代から、「腕」を尊重する風土への回帰
古典経済学の思想史から見える「お金」の不思議
著者等紹介
内山節[ウチヤマタカシ]
1950年、東京生まれ。哲学者。『労働過程論ノート』(1976年、田畑書店)で哲学・評論界に登場。一九七〇年代から東京と群馬県上野村を往復して暮らす。NPO法人・森づくりフォーラム代表理事。『かがり火』編集長。「東北農家の二月セミナー」「九州農家の会」などで講師を務める。2010年4月より、2015年3月まで立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まさにい
3
新潮選書版で読む。この著者である内山節氏はすごいなぁと思った。この本は、経済学のテキストであると共に、貨幣を哲学する本でもある。ペティ、ケネー、ロック、アダムスミス、リカードゥ、JSミル、ヘス、マルクス、ケインズ等の著作を元にその時代背景と市場経済の様子がよくわかる。福田歓一の政治学史と併せて読むとその時代が見えて来るようで非常に役に立った。2023/04/29
rymuka
3
この本を読み、貨幣は重農主義的にもなり得たのだと思った。1971年のドルショック以降、貨幣のグローバル化が急進したけれど、それによる固定観念を反省。他にも、村で家を買う話などがあり、示唆に富む! 読書録あり → http://rymuka.blog136.fc2.com/blog-entry-75.html2019/11/17