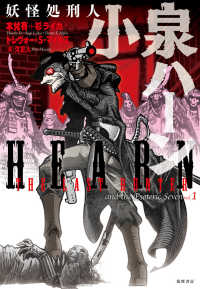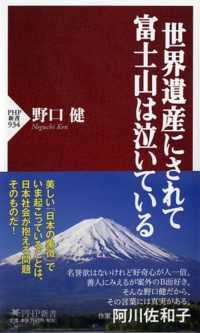著者等紹介
角田公次[ツノダトモジ]
1938(昭和3)年群馬県に生まれる。1959年より蜂を飼いはじめ、養蜂歴半世紀を超える。この間、アカシア、ウメ、クリなどさまざまな蜜源植物を植林してきた。元・群馬県養蜂協会副会長。2002(平成14)年に群馬県知事より県民功労賞。2008(平成20)年に日本養蜂はちみつ協会から地方功労賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
331
農文協の「農家になろう」シリーズの第2弾。今回は養蜂家角田公次の登場である。私事になるが、私はこれまでに養蜂家の人を見たことがない。仕事の内容はなんとなく想像がつくような気がしていたが、それは全体のほんの一部だった。この人は妻と共に赤城山楼で養蜂場を営んで50年になるらしい。現在は60群の巣箱を管理しているらしい。蜜蜂に役割分担があり、内役蜂(巣の中で働く)と外役蜂に分かれていることも初めて知った。そうだったのかと思うことばかり。2024/01/15
Kawai Hideki
97
割と本気で農家になりたい人向けの、オトナの写真絵本。ミツバチやハチミツの美しい写真にとどまらず、専門用語や厳しい現実の苦労話も容赦なく出てくる。「蜂飼いは耳で花を見るんだ」「アカシアの花が咲くときに、蜂の数が最高に増えるようにするのが、蜂飼いの腕のみせどころなのさ」「蜂飼いのくらしは花とともにある。花のことを知らずに蜂は飼えない。」なと、名言多し。娘は、分蜂したミツバチの大群と、ミツバチの宿敵スズメバチをピンセットで捕らえた写真がお気に入り。2015/12/20
kinkin
52
先日、近くの山のふもとでミツバチの巣箱がいくつも置かれているのを見かけたので、ミツバチのことが知りたくなり読んだ。著者は現役の養蜂家。養蜂という仕事のこと、ミツバチの生態がわかりやすい。描かれていた事を一部まとめてみるとみつばち一匹の重さは約0.1g、生まれてから死ぬまでに数千キロを飛び、それで一生かけて集めるはちみつはスプーン一杯分という記述が印象に残った。他スズメバチとの戦いなども書かれている。写真も美しかった。図書館本。2015/11/18
Toshi
18
蜂蜜と言うとレンゲやアカシアを思い浮かべるが、当たり前だがミツバチは冬を除いて年中活動しており、春はサクラやナノハナ、初夏はアカシア、夏はカキやクリ、そして秋にはソバやウドの蜜を集めるという。そして冬を越し、また春を迎える。「ミツバチは人と花の間をつないでくれるもの。」養蜂家角田さんのこのシンプルな言葉に、人と自然の共生のあり方が表現されている。いやーミツバチ育ててみたいです。まず花カレンダー作らないと。この本も農文協「農家になろう」のシリーズです。2024/01/17
tonpi
13
子供用の本ですね、でも大人でも楽しめますよ(^^♪2018/05/15