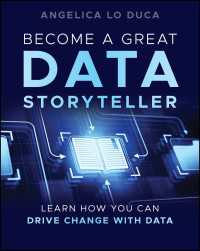目次
第1章 津波―「高崎浦地震津波記録」を読む(元禄の大地震で津波が襲う;夜中におきた大地震 ほか)
第2章 洪水―「大水記」を読む(江戸で学んだ名主・奥貫友山;享保十二年の洪水―父の行動を間近に見る ほか)
第3章 飢饉―三大飢饉の記録を読む(享保の飢饉;天明の飢饉 ほか)
第4章 噴火―「浅間大変覚書」を読む(各地の被害;「浅間大変覚書」を読む ほか)
第5章 地震―「弘化大地震見聞記」「善光寺地震大変録」を読む(大久保董斎の体験;中条唯七郎の体験)
著者等紹介
渡辺尚志[ワタナベタカシ]
1957年、東京都に生まれる。1988年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。現在、一橋大学大学院社会学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちゃま坊
16
江戸時代の津波、洪水、飢饉、噴火、地震の農民による記録。災害復興の教訓が書かれている。米の援助は備蓄保存してしまう者がいる。すると本当に必要な人に渡らなくなる。備蓄できない炊き出しにするのが正解。災害後の物資の買い占め問題と同じだ。2020/01/31
1.3manen
3
新刊棚より。「大地震のあとには必ず津波が来る」とは経験則のようである(20頁~)。それで高台避難は正しい判断であったのだ。貪欲な民衆、不十分な救済(56頁)とは、東電からの不本意な賠償金のようなものであろうか。時代は変わっても、構造的なものは残ってしまうのか。享保年間で、富裕者は困窮者に恵むのだが、それも限界に達し、飢饉は弱者には苛酷であったという(82頁)。極限状況下では人肉を食べるという共食いも・・・(91頁)。これには閉口。時代が示唆する後世の人間への教訓こそが、史学の存在意義。暗記科目ではない。2013/05/04
井上岳一
0
江戸時代の村の様子を知りたくて読んでみた。江戸時代には災害が頻発するが、自然災害の多くが、また人災の側面を持っていたことが、この本を読むとよくわかる。商品経済に合わせた商品作物づくりが、飢饉の発生を助長した、など。飢饉は悲惨だ。飢饉の際の奪い合いの様相は凄惨だ。人肉食についての記述もある。そういう禁を犯した人々に対する制裁の方法もまた凄い。本書を読むと、農村生活が決して牧歌的なものではなかったことがよくわかる。2015/09/19
平田剛
0
「日本人は災害からどう復興したか」渡辺尚志。。。。「そもそも、人間にとって最大の災難は飢饉である」。。。人びとの生活は。。。どんどんよくなり贅沢の限りを尽くすようになった。老若男女ともに、何より恐ろしい飢饉の辛さを忘れ、無為に月日を送る者ばかりが増えてきた。(アベノミクス要注意@ Sun.)2013/05/08