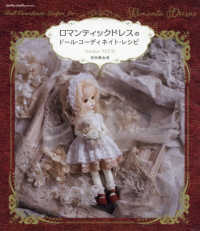内容説明
大胆不敵、傍若無人…いったいなぜ動物たちはこれほど大胆な行動をとるようになったのか。
目次
1章 変わりゆく動物地図―自然環境の変化を受けて(ノウサギ盛衰記;「幻の動物」はいま ほか)
2章 外来動物、勢力拡大中―日本の自然に溶け込む(空飛ぶハクビシン;マングースに土日はない ほか)
3章 現代の山の幸―「餌づけ」って何?(田畑に集う動物たち;フルーツ天国 ほか)
4章 人間なんて怖くない―人慣れした新世代動物(傍若無人なサル;トラクターに群れるアマサギ ほか)
5章 サインを読みとくヒント―野生動物と向き合うために(「松枯れ」というサイン;足跡で読む動物の心理 ほか)
著者等紹介
宮崎学[ミヤザキマナブ]
1949年、長野県に生まれる。精密機械会社勤務を経て、1972年、独学でプロ写真家として独立。中央アルプスを拠点に動物写真を撮り続け、「けもの道」を中心とした哺乳類、および猛禽類の撮影では、独自の分野を開拓。現在、「自然と人間」をテーマに、社会的視点に立った「自然界の報道写真家」として精力的に活動している。土門拳賞、日本写真協会年度賞、講談社出版文化賞など、数々の賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
47
とても興味深く読むことができた。最近野生動物が里にやってきて作物を食べたり、人に危害を与えるといったニュースが多い。山の開発が大きな原因だと思っていたが実はそれ以外にも理由がたくさんあることを知った。著者はそんな課題を写真と解説でわかりやすく解説するとともに、今後課題についてどう対処すべきか、また動物との関わり方についても書いている。野生動物のフィールドワークや生態写真の第一人者である著者ならではの本だと感じた。おすすめの一冊。図書館本。2015/05/11
yumiha
25
『ツキノワグマ』と同じ著者。本書でも、どうしたら野生生物と共存できるのか?という問題提起を写真も含めて、書いておられた。墓のお供えをかわるがわる食べにくるサル・ツキノワグマ・ハクビシンの写真は、失笑してしまう。棄てられたスイカに集まるイノシシなど、人間の不用意な行動が野生動物をいかに引き寄せているか、考えさせられた。また人家の近くの熊棚の写真も、なんて無防備、と思った。私も含めて身の回りにいる野生動物について知らないことの自覚が足りないのだと思う。そこが共存の第一歩だ。2016/10/01
あんこ
13
房総半島全体に広がってしまったキョン。ハクビシンはうちの区でもいるみたいだし。お墓のお供えものを食べる猿やクマ。一番驚いたのは、中央高速の脇にいるクマの写真。こんな近くまで来るのかと。野生動物との共存について、深く考えさせられる本だった。2017/01/29
mshiromi
9
自然に囲まれて生活しているという事に意識を向けさせてくれる。1960年前後の国策国有林民有林全国一斉伐採で生態系かわる。絶滅危惧種の動物たちは増え人間にとってやっかい者になったり、また森林が育つと彼らは徐々に減り、生態系を変える。強く生きれるものは生存競争で培ったノウハウで人工物にも生きる術を見いだす。外来種に囲まれたお城、夜な夜なフラッシュをたかれ決定的瞬間を撮られた動物たち、人なんて怖くない。受け入れ難なくやり過ごすように見える姿も人知れず、、自然に馴染むのは最良のいきかたなのかもしれない。2015/07/23
ココアにんにく
7
「人間の無関心・無防備」という言葉が何度も。餌付けの問題は近所でもありますが、廃棄果物や牧草、桜の木、そして凍結防止剤まで結果として餌付けになっているということ。塩化カルシウムが鹿やノウサギのミネラル補給源になっていたとは。野生生物にとってもはや怖い存在ではなくなった人間。カラスや夜ハト、餌付けキタキツネなど環境に順応しているとも思えます。人間と自然の関係。そもそも人間も自然の一部なので結論の出ない問題だと感じました。リアルな野生写真が多くて熟読。お供えの梨を取る猿の目線が墓石を拝んでいるように見えるw。2016/10/29
-

- 電子書籍
- この運命に逆らってみます~転生先は寵愛…
-
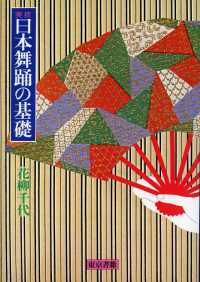
- 和書
- 実技日本舞踊の基礎