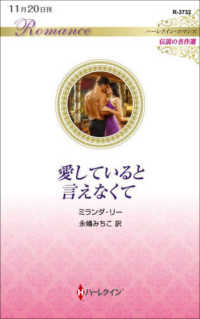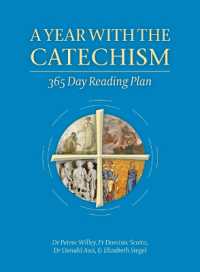内容説明
ふだんどこにいて、何を食べ、年に何回世代交代しているのか?いったい、畑や庭にどれだけいるのか?塩で溶かすや、ビールで大量誘殺は本当に効果的なのか?これまであまり知られることのなかったナメクジの本当の姿と、効果的な防ぎ方を紹介。
目次
1 ナメクジとは(殻がない陸の貝;日本にいるナメクジ ほか)
2 ナメクジの生活史―本当のその暮らしぶり、生理生態(特異な姿かたち;好きな環境、好きな食べ物 ほか)
3 まちがいだらけのナメクジ防除(こんな対策、していませんか?;「誘引して殺す」の発想はまちがいでないけれど ほか)
4 これならできるナメクジ防除―効果をきちんと出すやり方(害虫の防除効果の測り方;対象害虫は何匹いるの?―生息個体数を推定する ほか)
著者等紹介
宇高寛子[ウダカヒロコ]
1980年大分県生まれ。大阪市立大学大学院理学研究科後期博士課程修了、博士(理学)。現在、大阪市立大学大学院理学研究科特任講師。チャコウラナメクジを中心に無脊椎動物の季節適応を研究
田中寛[タナカヒロシ]
1955年大阪府生まれ。京都大学大学院農学研究科博士課程修了、博士(農学)。1985年から大阪府農林技術センター(現大阪府環境農林水産総合研究所)に勤務。各種農作物・緑化樹等の総合的害虫管理(IPM)を中心に研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とんかつラバー
14
学者と農林センターの両者による有効的なナメクジ退治法。駆除剤が販売されている割にはナメクジの生態はあまり解明されていなかった。ちなみに「天然素材でやさしい」系のナメクジよけは効果もないし全然やさしくない(魚とか死ぬ。発ガン性物質も含まれてる)勝利への鍵は正しいタイミングで駆除剤(ナメキール等)の利用。ナメトラのように容器に駆除剤を入れて出られなくするトラップ型は効果が分かって良い。薬を使いたくない方は堆肥置き場にビニールをかける方式が有効2023/10/25
魚京童!
14
「けもの」以外の動物たちを親しみも込めて虫と呼ぶ習慣がある。その習慣にしたがった。2014/08/30
kenitirokikuti
8
図書館にて。2010年刊行。農文協の本である。われわれがよく見る「チャコウラナメクジ」(本体薄茶色で背中に黒筋ある)は、アメリカザリガニと同じく外来種である。ナメクジはおもに動植物の死骸を食べる。単に匂いであり、生きたものでも食べはする。ナメクジ自体は清潔ではないものの、有毒でもない。ヒトの口内の方がはるかに雑菌が多い。ミミズと同じでその辺にたくさんいてじわ増えしてじわじわ移動してくるので、根絶には手間がかかるだけ。害はないけど、素足で踏んづけるとキモい。2019/09/01
新天地
4
趣味と実益を兼ねた面白い読書だが、ナメクジの写真をまじまじと観察するのは結構精神にくるものがあった。ナメクジの生態は研究者の間でもほとんど知られていないものだそうでこの本の執筆過程で、ビールトラップは有効だがコスパが悪すぎるといった当たり前の対策も実は的外れ等の多くの事が解ったらしい。確かに考えてみれば自分の家の畑でも邪魔で厄介だけども、深刻な被害は及ぼさないので、他の病害虫のついででしか対策はしてこなかった。「地図カルテ」のアイデアはほかの病害虫管理にも応用できるのでぜひ活用したい。2019/10/18
Hiroyuki Nakajima
3
キャベツが被害に有ってしまい、勉強の為に借りました、生態に関しては学ぶ所が多かったのですが、農薬の研究者の方が書かれた本なので対策に関しては無農薬派の自分にはあまり役に立ちませんでした。ナメクジがビールを好むのは植物が発酵した時に作られるアルコール成分の香りからと言うことでした2011/09/26