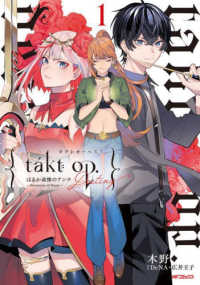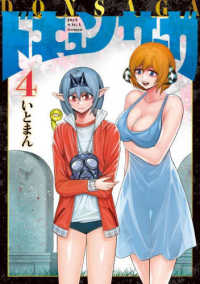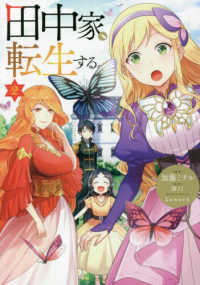- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(海外)
内容説明
事実、なぜ世界中がフランス料理について、かくも語り、書き、興味を示すのか?ギロチンの後の楽しい宴から、タレーランの晩餐会、そして、言葉で味付けするヌーヴェル・キュイジーヌの秘儀、果ては、肥満や狂牛病までを縦横無尽に通覧する、画期的フランス食文化論。
目次
序章 食卓で語ることの楽しさ、食を語ることの困難
第1章 階級社会とフランス近代の食文化
第2章 消費社会の成立とフランス食文化
第3章 食事の形式の成立と規範化―フランス・ガストロノミーの基盤は何であったか
第4章 豊かさと格差の中でのフランス食文化
第5章 グローバル化の中でのフランス食文化―不安の中の食文化
第6章 なぜ食はパリなのか
著者等紹介
北山晴一[キタヤマセイイチ]
1944年東京都生まれ。東京大学大学院博士課程修了。クレルモン・フェラン大学、パリ第三大学留学。立教大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
俊介
7
フランスの食文化に対し、社会学的な観点からの考察を試みた、なかなか硬派な一冊だった。フランス料理の歴史、現代フランスが抱える食のリスクなど、切り口は幅広いが、やはりメインの論考は「なぜフランスの食文化は長期間にわたり世界の模範になり得たか」という部分だろうか。著者は、ある意味スタンダードなこの問いに、数々のフランス語原典からの参考文献を引きながら、キリスト教や錬金術などと絡めて議論を進める。社会学の本領発揮といった感じで面白かった。ヌーベルキュイジーヌについても、割と深く掘り下げてあったので参考になった。2019/11/04
かえ
0
図書館2015/05/26
もけうに
0
論文を読んでいるようで面白くなあああ~~~~い。カタカナ語使いすぎ。もっと噛み砕いて読み物として面白いものが読みたい。論文としては知らんけど、読み物としては駄作です。2014/01/07