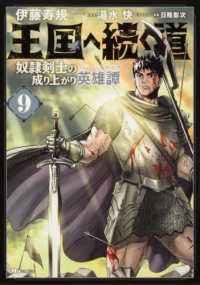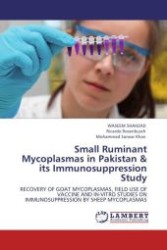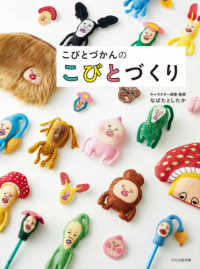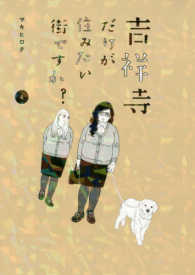目次
煮豆をワラで包むとなっとうができる!
聖徳太子に加藤清正、納豆太郎糸重ここにあり
なっとうは季節商品。江戸のなっとう売り
なっとうになって消化もよく、栄養もふえた!
糸引きなっとう、浜なっとう、テンペにキネマ
納豆菌が大豆をなっとうにする原理
なっとうの原料は大豆と納豆菌
用意する道具と全体の手順
ワラづとなっとうをつくってみよう(1日目)
ワラづとなっとうをつくってみよう(2~3日目)
純粋培養の納豆菌を使ってつくろう
テンペをつくろう
大豆の発芽率試験、吸水テスト、コップで観察
なっとうの糸はどこまで伸びる?
なっとうを使った料理いろいろ
著者等紹介
わたなべすぎお[ワタナベスギオ]
1930年生まれ。宇都宮大学農学部農芸化学科において発酵専攻。以降、アルコールならびに醸造工業の試験研究などに携わる。現在、鈴与工業株式会社に勤務。納豆生産技術の開発に従事。取締役企画室長。平成元年より平成9年まで、農林水産省食品総合研究所発酵食品講習会において“無塩発酵大豆食品(納豆)”の講座を担当
さわだとしき[サワダトシキ]
1959年青森県生まれ。阿佐ヶ谷美術専門学校卒業。デザイン会社K2勤務を経て独立。絵本「アフリカの音」(講談社/96年日本絵本賞)、「ほろづき」(岩崎書店)。共著に「てではなそう・きらきら」(小学館/第8回日本絵本賞読者賞)などがある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Aya Murakami
61
図書館本。 なっとう…、嫌いな食べ物(いちおう食べ物とは認識している私)。そしてやはりというべきか東でよく消費されて西ではあまり消費されないらしいです。ただし九州ではたくさん消費されているとか?なっとうとは臭くて糸を引くものと思い込んでいましたが、糸をひかないなっとうもあるそうな。母曰く「昔はあんたも食べていた」そうですが、ためしに食べてみると懐かしいながらやはりおいしくなかったです。健康効果はやはり整腸作用に血液サラサラ…だそうです。2024/07/13
FOTD
25
納豆は無塩大豆発酵食品(塩を使わないという点ではネパールのキネマ、インドネシアのテンペ、と同様)。この本は納豆の歴史に始まり、納豆菌が大豆を作る原理が述べられ、後半には納豆の作り方が詳しく記載されている。用意する道具、全体の手順もわかりやすいイラストとともに説明あり! 作れそうな気になる。 藁が手に入らなくても、市販の納豆から納豆菌を取り出して、納豆を作る方法もある。今の季節だからか、ふと思ったのだが、お子様の夏休みの自由研究にも良いかもしれない。2023/07/28
ふじ
19
農文協のこのシリーズは、児童書なのに情報量もありかなりためになる。なっとうが煮大豆とワラだけでできるとは!納豆菌ってどこから調達すればいいの?と思っていたが、ワラについてるとな。稲作地のこの辺じゃ作り放題じゃない。ただし、別の菌が入らないように煮沸殺菌が必要。そこが難しい。何しろ菌は目に見えないからね…失敗したらどんな味になるやら、と思うとなかなか勇気がいる納豆作りなのでした。2021/03/10
Go & Mocha
9
詳しい解説の中で「なっとうを作ったら記録する」というフレーズが気に入った。このシリーズは楽しい。いろいろと作ってみたいという意欲がわいてくる。次行ってみよう!2016/03/24
訪問者
4
わらづと納豆はなかなか美味しい。わらの見た目だけではないのだ。2022/04/10