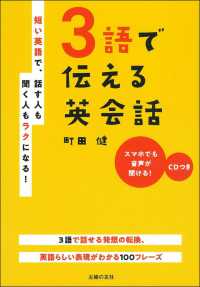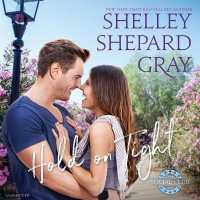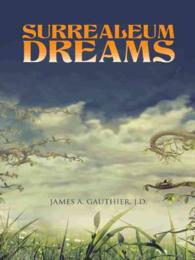目次
1 遊び日のありよう(年間の定例遊び日;遊び日の生活内容)
2 増大する遊び日(祭礼遊び日の増加;定例労働休日の増加;願い遊び日・勝手遊び日)
3 規制をのりこえる潮流(規制の埒外の時代―近世前・中期;遊び日化規制の時代―近世後期)
著者等紹介
古川貞雄[フルカワサダオ]
1931年長野県上高井郡小布施町生。信州大学教育学部卒業。長野県史主任編纂委員、長野県立歴史館学芸部長等を経て、現在長野市誌編さん主任。専攻、日本近世史
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ずしょのかみ
1
「遊び日」は神まつりの日であったことは民俗学の成果から明らかである。神をまつることを遊ぶと表現した。ただ、近世のころにはだいぶこの風習が廃れたようで、単に休日として痕跡を残しつつあった。 本書は「遊び日」の、神まつり的な内容ではなくて村内における機能を考察し、村の自治を明らかにした。史学と民俗のあいだに立って読むと、たいへんおもしろい2018/11/20
ymazda1
1
学校で教えていただいた江戸時代の農村像ってのが、なんかずっとピンと来てなくて、江戸時代の農村の状況を客観的数値的に捉えた本を探してたときに見つけて読んだ本。。。 いまちょっと調べてみたけど、慶安御触書とか、教科書から消えつつあるのか。。。
-
- 洋書
- Faking It