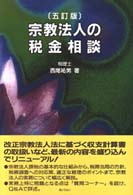出版社内容情報
抽象的な代数学への第一歩を、まず体上の線形空間を導入した上で線形空間の概念を環上の加群へ一般化するという、体→環→群の順に導入する流れで学んでいく。具体的な目次立ては以下の通り。
第1章 体上の加群(別名:線形空間または
ベクトル空間)
第2章 一変数多項式環上の加群
第3章 環上の加群
第4章 有理整数環
第5章 一変数多項式環上の加群の計算理論
第6章 加群理論の応用
第7章 可換群から非可換群へ
第1章では体係数の線形空間を導入し短完全系列を用いて種々の次元公式を導く。第2章では行列の固有値の理論を一変数多項式環上の加群の理論として見直す。第3章では体の公理から除法の公理を削って可換環の公理を、乗法の交換法則を削って環の公理を導入し、次に群の公理を導入して加群と環上の加群を定義する。第4章では高校で学ぶ整数の性質の厳密な取り扱いを説明し、Smith標準形を与える。第5章では一変数多項式環に対し第4章と並行した性質が成り立つことを説明し、有限階自由加群のあいだの準同型の核と余核の計算方法を説明する。第6章では有限生成Abel群の構造定理、Jordan標準形・Cayley-Hamiltonの定理・Sylvester方程式の加群を用いた取り扱いを説明する。また有限Abel群の部分群を求める計算方法を説明する。ここまでは(環の作用をもつ)加法群しか出てこないが、第7章では非可換群の正規部分群による商や群作用を導入する。
全編に渡り豊富な例が与えられ、つねに計算方法が提示される。また、他書に見られない広い視野から多くの事実が註として付記されており、代数学の数学の諸分野へのつながりがわかるとともに線形代数の見方が一変するであろう。
章末問題や計算問題も豊富で、手を動かしながら概念を身につけたい人や代数学を学び直したい人への独習書としても最適の一冊。
内容説明
抽象的な代数学への第一歩を、環上の加群を中心に体→環→群の順に導入する流れで学んでいく。問題も豊富で手を動かしながら代数学の考え方が身につく一冊。
目次
第1章 体上の加群(別名:線形空間またはベクトル空間)
第2章 一変数多項式環上の加群
第3章 環上の加群
第4章 有理整数環
第5章 一変数多項式環上の加群の計算理論
第6章 加群理論の応用
第7章 可換群から非可換群へ
著者等紹介
有木進[アリキススム]
1959年下関市に生まれる。1989年理学博士(東京大学)。東京商船大学(現・東京海洋大学海洋工学部)、京都大学数理解析研究所を経て、大阪大学大学院情報科学研究科教授。専門は、ヘッケ環、量子群、代数群の表現論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。