出版社内容情報
日本数学史研究を国際的水準に高めた歴史家の膨大な著作から、未来の世代へと継承されるべき珠玉の諸論文を精選し、一望のもとに。日本数学史研究を国際的水準に高めた歴史家の膨大な著作から,未来の世代へと継承されるべき珠玉の諸論文を精選し,一望のもとに。第1巻では、三上義夫の江戸期の数学史論考を中心に集録。
一 研究回顧録
1.新編「和漢数学科学史研究回顧録」(藤井貞雄編・柏崎昭文補訂)
1.支那の数学
2.支那日本の科学史
3.支那軍事科学史
4.支那数学史
5.日本測量術史
6.文化史上より見たる日本の数学
7.関孝和伝の研究
8.会田安明伝並びに山形二本松地方の最上流諸算家
9.諸算家事跡
10.信州の諸算家
11.上州の諸算家
12.北武蔵の諸算家
13.房総の諸算家
14.江戸の諸算家
15.増修日本数学史の校訂と日本数学編年史
16.和漢科学史年表
17.林博士和算研究集録の批判
和漢数学科学史研究回顧録 補遺
7.関孝和伝
18.日本数学史
5.日本測量術史
9.諸算家事跡
19.諸算家の地方分布
20.諸算家採訪記事
二 日本数学史概説
2.日本数学史
第一部
(1) 総説
(2) 支那の数詞
(3) 算木
(4) 算法
(5) 数学
(6) 天元術
(7) 四元術
(8) 演段術
(9) 点鼠術
(10) 方程と方程式
(11) 行列式
(12) 招差法
(13) 円の算法
(14) 円理
(15) 角術
(16) 累円術
(17) 整数術
(18) 方程式解法
(19) 規矩術と幾何学
(20) 円理豁術の諸問題
(21) 和算より洋算への推移
第二部
(1) 日本古代の数学
(2) 算盤の伝来
(3) 徳川時代に於ける数学の勃興
(4) 関孝和
(5) 関孝和と同時代及びその門下
(6) 関孝和直後の時代,円理の発達
(7) 安島直円とその時代
(8) 会田安明及びその時代
(9) 和田寧及びその時代
(10) 幕末の諸算家
(11) 幾何学の発達
(12) 西洋の影響
跋
三 日本伝統数学の基本概念
3.数学進歩の歴史――日支欧数学比較発展史
4.日本数学発達の由来
5.九々に就きて
6.十露盤と算木
7.我が国文化史上より見たる珠算
1.「そろばん」以前の計算道具
2.支那に於ける珠算の沿革
3.我が国への珠算の伝来
4.「そろばん」なる名称の由来
5.我が国に於ける「そろばん」の特異性
6.我が国の数学に及ぼした「そろばん」の影響
7.「そろばん」に関する文献
8.「そろばん」の諸流派
9.「そろばん」の額
10.明治九年の地租改正当時に於ける算者の事蹟
11.社寺に対する「そろばん」額奉納の意義
12.明治維新前後に於ける主なる算者及西洋数学の与えた影響の波紋
13.「そろばん」改革論
14.関孝和先生の事蹟と国定教科書
15.結語
8.點竄語源攷
9.日本に於ける代数学の発達
1.前記
2.江戸時代の数学
3.西洋数学の採用
4.江戸時代初期の状態
5.寛永より寛文頃の状態
6.支那に於ける天元術の状態
7.翻狂 関孝和
8.発微算法、演段術
9.見題、隠題、伏題
10.維乗、行列式
11.算法発揮の行列式展開法
12.久留島義太、菅野元健の展開方法
13.演段と点竄術
14.演段と点竄の区別
15.方程式解法
16.算顆術
17.不定方程式
18.代数記法
19.招差法
20.円の算法
21.円理
22.無限級数
23.廉術、逐索術
24.極大極小
25.微分法
26.西洋数学の伝来
10.数学上の帰納法について
四 行列式論考
11.日本の行列式につきて
12.石黒信由の行列式論
13.日本行列式研究の経過
14.行列式論
関孝和の方法
関孝和の方法の訂正.上.交式の訂正
関孝和の方法の訂正.下.斜乗法の訂正
逐式交乗
維乗
逐式交乗と『大成算経』
『算法発揮』
久留島義太及び菅野元健の展開法.附行列式論の終末
五 幾何学論考
15.日本数学上に於けるPythagorasの定理の証明
16.日本数学上に於けるCASEYの定理
17.梯内容楕円及四円術の拒否に関する和算家の論証並びに和算上の反形法
六 和算家事蹟
18.建部賢弘年譜
19.藤田貞資事蹟
20.古川氏清と至誠賛化流の数学
21.和田寧
七 日本数学外篇
22.算額雑攷
23.琉球古来の数学
24.我国における洋算の発達
八 日本数学教育史論考
25.日本数学教育史
1 緒論
2 奈良朝時代
3 中世の数学
4 毛利重能
5 『塵劫記』
6 初期の諸算書
7 天元術
8 関孝和
9 関流数学の伝授段階
10 関流伝授の五段階
11 関流最高の秘伝、『乾坤之巻』
12 関流諸算書の整頓
13 『拾?算法』と『精要算法』
14 関流と最上流の論争
15 最上流の成績
16 数学の諸流派
17 至誠賛化流
18 『点竄指南』『点竄指南録』『天生法指南』
19 『算法新書』
20 『求積通考』
21 和田寧と諸算家の入門
22 京坂の数学
23 京都の中根派
24 大島喜侍
25 大坂の宅間流
26 宅間流以外の大坂の諸算家
27 江戸末期の数学
28 遊歴算家の功績
29 遊歴算家と算法の伝授
30 諸算家の数学学習の状態
31 数学教授の事情
32 諸藩の藩校と数学
33 西洋数学の伝来
34 西洋数学の教授
35 維新後に於ける和算家の態度
36 数学者の輩出と数学教科の変遷
37 数学史と数学教育上の関係
26.数学教育上に於ける数学史の利用
?.はしがき
?.数学の教科と日本の数学
?.数学史の利用
?.正負
?.連立一次方程式
?.字母の記号
?.勾股法の定理
?.幾何学の名称
?.幾何学の歴史
?.代数学
??.盈?
??.円周率
??.関孝和の円周率の算法
??.ケージーに先だてるケージーの定理
??.数学史の総括的知識
佐々木力[ササキ チカラ]
柏崎昭文[カシワザキ アキフミ]
目次
1 研究回顧録
2 日本数学史概説
3 日本伝統数学の基本概念
4 行列式論考
5 幾何学論考
6 和算家事蹟
7 日本数学外篇
8 日本数学教育史論考
著者等紹介
三上義夫[ミカミヨシオ]
1875(明治8)年2月16日広島県高田郡上甲立村(現在、安芸高田市甲田町)有数の大地主、三上本家の安国に、十代目三上助左衛門安忠を父に、勝を母として生まれた。1890(明治23)年12月25日広島県広島市広島高等小学校高等小学科卒業。1891(明治24)年4月千葉県尋常中学校二年級入学。1895(明治28)年4月国民英学会・東京数学院をともに卒業。1896(明治29)年5月21日近藤タケと結婚(義夫21歳、タケ17歳)
佐々木力[ササキチカラ]
1947年宮城県生まれ。東北大学理学部と同大学院で数学を学んだあと、プリンストン大学大学院でマイケル・S・マホーニィやトーマス・S・クーンらから数学史並びに科学史・科学哲学を修学、Ph.D.(歴史学)。1980年から東京大学教養学部講師、助教授を経て、1991年から2010年まで教授。定年退職後、2012年から北京の中国科学院大学人文学院教授。中部大学中部高等学術研究所客員教授。東アジアを代表する数学史家
柏崎昭文[カシワザキアキフミ]
1957年岩手県生まれ。早稲田大学第一文学部人文専攻卒業、東京理科大学理学部二部数学科卒業。その後、東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系にて数学史を専攻、2005年博士課程単位取得退学。三上義夫の生涯と業績の研究が専門。東京理科大学非常勤講師。啓明学園中学校高等学校非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
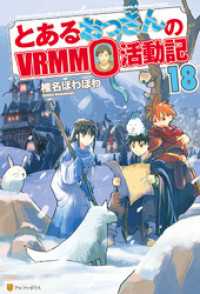
- 電子書籍
- とあるおっさんのVRMMO活動記18 …






