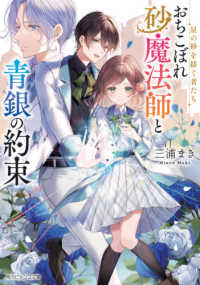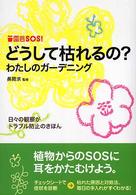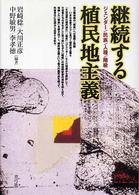出版社内容情報
日本の人口減少と高齢化の進行などの現実を直視し、「限界都市化」に抗した持続可能な都市機能を実現するための方策を探る。
はしがき
執筆者紹介
序章 連携アプローチから考察するローカルガバナンスと地域レジリエンス
1 LORC研究と本叢書の位置づけ
2 ローカルガバナンスの実在概念化にむけて
第1部 自治体連携アプローチ --- 地域資源の最適化を図る
第1章 都市圏ガバナンスの昨今 ---アメリカのグローバル化に対峙するNew Regionalis
1-1 都市圏の変容
1-2 都市vs.郊外小史
1-3 New Regionalism (新しい都市圏主義)の時代
1-4 アメリカ vs.カナダ
第2章 ツインシティズ都市圏におけるガバナンス --- Metropolitan Councilを中心に
2-1 アメリカにおける都市圏ガバナンスへの注目
2-2 スマート・グロースの展開
2-3 Metropolitan Council
2-4 都市圏ガバナンスの課題
2-5 わが国への示唆
第3章 アメリカにおける広域都市圏の形成と役割
3-1 アメリカの広域都市圏形成の流れ
3-2 戦前から戦後にかけての5大人口流動
3-3 1950~60年代の広域調整・広域連携
3-4 1970年代の広域調整・広域連携を大きく規定した連邦環境政策法(NEPA)
3-5 1980年代の広域調整・広域連携
3-6 1990年代以降の広域調整
3-7 スマート・グロースの優等生ポートランドMETROにおける都市圏ガバナンスの役割変遷
3-8 民間経済団体等が中心となった広域調整・連携
3-9 アメリカ広域都市圏の展望
第4章 EUにおける都市政策の多様化と計画対象の広域化
4-1 はじめに
4-2 欧州の二極化する人口動態
4-3 広域圏のプランニング
4-4 結束政策:条件不利地域や社会的弱者の重視
4-5 ノウハウの共有と開発、成果の普及・還元:多様化するURBACT
4-6 まとめ
第5章 イギリス大都市圏の広域自治体 --- シェフィールド・シティ・リージョンを事例として
5-1 イギリス大都市圏の広域自治体に対する本章の視角
5-2 イギリス大都市圏の広域自治体の変遷
5-3 シェフィールド・シティ・リージョンを巡る論点
5-4 イギリス大都市圏の広域自治体の経験が日本に与える示唆
第6章 地域資源の最適化を図る --- 東三河地域におけるマルチ・レベル・ガバナンスの様相
6-1 はじめに --- マルチ・レベル・ガバナンスへの着目
6-2 東三河地域におけるマルチ・レベル・ガバナンス
6-3 大きな連携 --- 三遠南信地域連携
6-4 小さな連携 --- 豊根村の挑戦
6-5 おわりに --- マルチ・レベル・ガバナンスの可能性
第2部 パートナーシップアプローチ --- 地域アクターの有機的な連携を図る
第7章 英国の「パートナーシップ文化」のゆくえ ---「ビッグ・ソサエティ」概念の考察から
7-1 英国のパートナーシップ政策研究
7-2 福祉国家モデルの解体から新自由主義政策、そしてパートナーシップ政策へ
7-3 「第三の道」と新労働党政権
7-4 「ビッグ・ソサエティ」概念におけるローカリズムの考え方と実現のための政策
7-5 英国の「パートナーシップ文化」のゆくえ
第8章 持続可能な次世代地方都市のかたち --- 地域力再生に向けた地方都市ネットワーク「スロー・シティ連合」
8-1 中山間地域が社会に果たす役割
8-2 スロー・シティ --- 豊かな暮らしを実現するための自発的自治体ネットワーク
8-3 スロー・シティと日本の農政の課題
8-4 日本の地方都市に求められるもの
第9章 野洲川流域における流域ガバナンスと地域間連携
9-1 「人口減少時代」における流域ガバナンス
9-2 「鳥の眼」と「虫の眼」
9-3 農村コミュニティの調査
9-4 地域の「しあわせ」と流域ガバナンス
9-5 「小さな空間ユニット」の連携
第10章 再生可能エネルギー事業にみる官民・民民連携 --- 地元企業・市民団体・大学イニシアティブの事例から
10-1 エネルギーをめぐる制度改革と自由化の波
10-2 再生可能エネルギーによる地域再生
10-3 地元企業イニシアティブ:小田原箱根エネルギーコンソーシアム
10-4 市民団体イニシアティブ:徳島地域エネルギー
10-5 大学イニシアティブ:プラスソーシャル
10-6 官民・民民連携がつくるローカルガバナンス
第11章 大学と地域の連携による「学びのコミュニティ」の形成 --- 京都発人材育成モデル「地域公共政策士」の取組から
11-1 大学/地域連携の取組への注目
11-2 京都発人材育成モデル「地域公共政策士」
11-3 大学と地域の連携による「学びのコミュニティ」
11-4 今後の展望 --- 「学びのコミュニティ」が機能するために
第3部 新たな時代の地域を構想する --- 地域資源の顕在化を図る
第12章 イギリスの社会的投資市場 --- 金融仲介機関を中心として
12-1 イギリスの社会的投資市場に対する本章の視角
12-2 イギリスの社会的投資市場の変遷
12-3 金融仲介機関の全容
12-4 金融仲介機関とほかの団体の関係
12-5 イギリスの社会的投資市場の経験が日本に与える示唆
第13章 コミュニティ・ファンドを通じた新たな地域の連携
13-1 はじめに
13-2 コミュニティファンドとは何か --- 市民コミュニティ財団の定義と役割
13-3 新たな地域の連携の結節点としてのコミュニティファンド
13-4 結節点から価値創出へ
13-5 「制度」のプラットフォームを担うコミュニティファンド
13-6 これからの展望
第14章 広域的な地理情報システムの利用による新たな自治体間連携の可能性
14-1 はじめに --- 人口減少社会における地理情報の活用
14-2 広域GISの既往研究
14-3 事例から見る広域GISの類型
14-4 広域ガバナンスにおけるGIS活用の可能性
終章 地域のレジリエンスを高める
1 現代社会におけるレジリエンス論の意義
2 本書の事例に見るレジリエンスの要素
白石克孝[シライシ カツタカ]
龍谷大学政策学部教授
的場信敬[マトバ ノブタカ]
龍谷大学政策学部准教授
阿部大輔[アベ ダイスケ]
龍谷大学政策学部准教授
目次
連携アプローチから考察するローカルガバナンスと地域レジリエンス
第1部 自治体連携アプローチ―地域資源の最適化を図る(都市圏カバナンスの昨今―アメリカのグローバル化に対峙するNew Regionalis;ツインシティズ都市圏におけるガバナンス―Metropolitan Councilを中心に;アメリカにおける広域都市圏の形成と役割;EUにおける都市政策の多様化と計画対象の広域化;イギリス大都市圏の広域自治体―シェフィールド・シティ・シージョンを事例として;地域資源の最適化を図る―東三河地域におけるマルチ・レベル・ガバナンスの様相)
第2部 パートナーシップアプローチ―地域アクターの有機的な連携を図る(英国の「パートナーシップ文化」のゆくえ―「ビッグ・ソサエティ」概念の考察から;持続可能な次世代地方都市のかたち―地域力再生に向けた地方都市ネットワーク「スロー・シティ連合」;野洲川地域における流域ガバナンスと地域間連携;再生可能エネルギー事業にみる官民・民民連携―地元企業・市民団体・大学イニシアティブの事例から;大学と地域の連携による「学びのコミュニティ」の形成―京都発人材育成モデル「地域公共政策士」の取組から)
第3部 新たな時代の地域を構想する―地域資源の顕在化を図る(イギリスの社会的投資市場―金融仲介機関を中心として;コミュニティ・ファンドを通じた新たな地域の連携;広域的な地理情報システムの利用による新たな自治体間連携の可能性)
地域のレジリエンスを高める
著者等紹介
白石克孝[シライシカツタカ]
1957年生まれ。名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得、修士(法学)。名古屋大学法学部助手、龍谷大学法学部助教授、同教授を経て、龍谷大学政策学部教授。龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)センター長
的場信敬[マトバノブタカ]
1973年生まれ。英国バーミンガム大学都市・地域研究センター(CURS)Ph.D.課程修了。Ph.D.in Urban and Regional Studies。(特活)グラウンドワーク福岡主任研究員、龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)博士研究員を経て、龍谷大学政策学部准教授
阿部大輔[アベダイスケ]
1975年生まれ。東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修了。博士(工学)。政策研究大学院大学研究助手、東京大学都市持続再生研究センター特任助教を経て、龍谷大学政策学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。