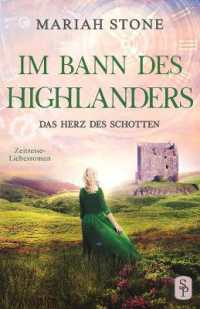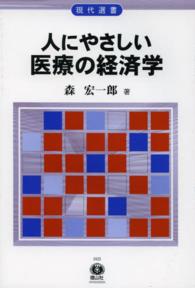内容説明
男たちは戦場へ行った。少女たちがチンチン電車を運転した。そして8月6日の朝がやってきた。いまよみがえる「チンチン電車被爆秘話」。
目次
第1章 「幻の女学校」との出会い
第2章 広島電鉄家政女学校開校
第3章 女学生運転士の誕生
第4章 青春の日々
第5章 軍都・広島とチンチン電車
第6章 八月六日、午前八時一五分
第7章 地獄絵のなかを
第8章 復旧電車が走る
第9章 女学生たちの六〇年
著者等紹介
堀川恵子[ホリカワケイコ]
1969年広島県生まれ。1992年広島大学総合科学部卒業。広島テレビ放送にて報道記者、ディレクターを兼務。経済ドキュメンタリー・平和問題などを多く手がける。2004年同報道部デスクを最後に退社、東京にて番組制作にたずさわる。ドキュメンタリージャパン専属ディレクター。おもな制作番組―『ニッポンの筆 世界に挑む』2003年、日本テレビ系列、ギャラクシー賞選奨、民間放送連盟賞優秀賞。『チンチン電車と女学生』2003年、日本テレビ系列、放送文化基金賞(ドキュメンタリー番組賞)、民間放送連盟賞最優秀賞。『千羽鶴はこうして集まった』2004年、日本テレビ系列、厚生労働省児童福祉文化財推薦
小笠原信之[オガサワラノブユキ]
1947年東京生まれ。1971年北海道大学法学部卒業。1972年北海道新聞記者を経て、86年フリーに。1990年『塀のなかの民主主義』(潮出版社)で第9回潮賞ノンフィクション部門優秀作受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。