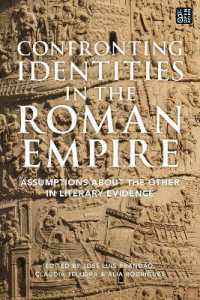- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
出版社内容情報
「つながれなさ」を通じてつながるために。当事者研究会に集う人々の「生きづらさ」とそこでの対話実践をフィールドワークから描き出す。
内容説明
「答えの出ない問いに向き合う」という豊かさ。弱さを抱えることは、誰にでも必ずある。「生きづらさ」の当事者研究におけるリアルな対話実践を、葛藤も含めて描き出す。
目次
誰もが「生きづらく」なりうる社会
第1章 「生きづらさ」とは何か
第2章 当事者研究を引き受けるために
第3章 づら研はどのような場か
第4章 「生きづらさ」とは何か
第5章 つながりの喪失・回復はいかに起こるか―インタビューを通じて
第6章 「私」とは誰か、「この場」とは何か
第7章 づら研では何が起こっているのか
終章 「生きづらさ」は連帯の礎になりうるか
著者等紹介
貴戸理恵[キドリエ]
1978年生まれ。関西学院大学准教授。「生きづらさからの当事者研究会」コーディネーター。専門は社会学、不登校の“その後”研究。アデレード大学アジア研究学部博士課程修了(Ph.D)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
56
【複雑さや真っ直ぐに行かないところこそが、自分の人生を生きることの汲み尽くせない豊かさである】不登校・ひきこもりなど多様な「生きづらさ」を持つ人々が集う当事者研究の場では、どのような対話実践が行われ、どんな葛藤が生じるかを描き出す書。巻末に、付録「生きづらさからの当事者研究」テーマ一覧、参考文献、索引。<本書では、フィールドワークを通じて「生きづらさ」を抱えた人の意味世界に迫るとともに、「生きづらさ」を、「自分には関係ない」と感じている人びとも含めた社会全体の連帯の基礎として、捉え直すことを目指す>と。⇒2025/04/16
katoyann
15
関西大学で開催されている「づら研」(生きづらさからの当事者研究会)をコーディネートする著者が執筆したエスノグラフィである。当事者研究の限界と可能性を探るという探索的な研究といえる。限界は、当事者性を強く訴える研究は問題を個人化してしまう点にあるとする。一方でその可能性は、共有されたマイノリティ属性でもはや問題を語ることができない社会にあって、多声性を担保しながら社会問題を見つめることにあるという。しかし、私は論点設定や結論が牽強付会だと思う。例えば、なぜ、ひきこもりと不登校を同じ文脈の中で語る必要があるの2025/02/14
きゅー
6
「生きづらさからの当事者研究会」でのフィールドワークをまとめた内容。全体的に散漫な印象を抱いた。サブタイトルにエスノグラフィとあるように、自身がコーディネーターとして参画する当事者研究への10年以上の参与観察を経て書かれたものだ。しかし、その10年の奥行きが伝わってこない。もちろん本書は人の生きづらさを解決するための手段を提供するものではない。人々がどのような生きづらさを感じ、それに対してどのように関われるかを綴ったものだ。ここで重要になるのは人々の声なのだが、聞こえてくるのは著者の学術的な問いと答え。2025/01/07