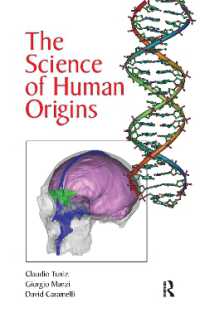出版社内容情報
「よい」教育とは何か。教育学はいかに「科学」たりうるか。有効な実践理論・方法をいかに開発するか。―そのすべてに“答え”を出す
内容説明
「よい」教育とは何か。教育学はいかに「科学」たりうるか。有効な実践理論・方法をいかに開発するか。―そのすべてに“答え”を出す。
目次
第1章 教育学の根本問題(何のための教育学研究なのか?;ポストモダン思想の隆盛 ほか)
第2章 メタ理論1 哲学部門―「よい」教育とは何か(現象学=欲望論的アプローチ;“自由の相互承認”および“一般福祉”の原理 ほか)
第3章 メタ理論2 実証部門―教育学はいかに「科学」たりうるか(科学性担保の理路;科学的価値の原理)
第4章 メタ理論3 実践部門―有効な実践理論・方法をいかに開発するか(諸実践理論・方法をめぐる信念対立の克服;目的‐状況相関的方法選択 ほか)
第5章 教育学のメタ理論体系とその展開(教育学のメタ理論体系;“教養=力能”とは何か? ほか)
著者等紹介
苫野一徳[トマノイットク]
哲学者・教育学者。熊本大学大学院教育学研究科准教授。早稲田大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
22
著者の本はいくつか読んでいる。これまでの集大成としての意気込みがある一冊。読んでいて面白くはある。「哲学部門」は過去本と同内容でフッサール現象学を基に構築していて、この部分の抽象的なメタ理論はよいと思う。結局は良い教育とは何かを話し合って共通理解を探るということになる。著者の回答として「自由、自由の相互承認、一般福祉」を挙げているがこの「自由」という語句はとても誤解しやすいと前々から思う。「実証部門」「実証部門」は新しいがこの部分に無理にメタ理論を導入して逆に理解しにくい。2022/03/10
いとう
7
教育学って学問なの?教育は為政者の意図が入り込み、科学のように普遍的な実証が難しく、分野ごとの成果主張が交錯していると感じていた。しかし、本書は教育学を学問として成立させるために、哲学・実証・実践の三部門に分け、それぞれに理念・原理・方法論を与えることで体系化を目指している。特に哲学部門では現象学的アプローチを基盤に「自由」「相互承認」「一般福祉」などの概念を提示し、教育の理念と方法論を明確にしている。このアプローチによって、教育学は学問としての地位を確立し、単なる道具にとどまらない可能性が示されている。2025/06/10
Nobu A
7
苫野先生著書3冊目。前著2冊は勉強になったが、今回は消化不良。何とも掴みどころがない。冒頭で「本著の目的は、『学問としての教育学』を体系化すること」とある。理由に教育学が細分化され、隣接領域でさえ知見を活かし合うことが困難な状況だと。前著でも詳述の「よい」教育とは何か、教育学研究は何の為にあるのか不透明だから体系化する意義があると。細分化されているのは教育学に限らず、そして他学は炳乎に体系化されているのだろうか。フッサールの現象学ではなく、他学との対比や現実の社会問題と絡めてもっと落とし込んで欲しかった。2022/09/22
かりん
4
3:《教育学を親学問として成り立たせるために》学問的に低く見られがちな教育学。それを克服するためのメタ理論を提示する。意欲的な取り組みの「熱さ」を感じた。内容は理解したつもりだが、己に学問的素養がないため、わかっていないかもしれない。個人的には広義の公教育というのがしっくり来ず、民間教育の立ち位置を考えた。細かい話では、意訳で言うと①高いエビデンスを誇る研究はそれゆえに無批判に受け入れられがち、②探究重視の入試は格差が広がると言われるが、だからこそ公教育でそれを保障すべきでは、というあたりが印象に残った。2024/07/19
Ken.
4
教育に携わるすべての人の共通言語になるべき一冊だと思います。第一章をはじめとする種々の問題は、私が大学院で学んでいた時も、いま学校で教育に携わっているときも痛感するものばかり。教育という複雑かつ細分化されてしまった営みを〈自由〉〈自由の相互承認〉〈一般福祉〉を底に敷いて徹底的に整理していく。これがみんなに「共通了解」され、建設的に子どもたちと向き合い、深く学んでいけたらどれほど楽しいだろう。わくわくする。「アブダクション」、「欲望-関心-目的相関的」に現れるという教育現象の性質など、注目すべきことは多い。2022/03/05