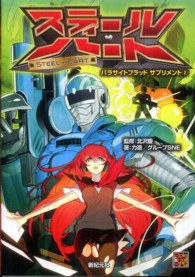出版社内容情報
子どものたちの“生活の場”である学校。そのなかで、心理職と教師がそれぞれの専門性を発揮し、協働して子どもにかかわるにはどんな工夫が求められるか。学校心理学の視点を活かした実践のポイントを丁寧に解説する。
目次
第1部 「チーム学校」とスクールカウンセラーの役割(学校を歩いて子どもと出会う;“生活の場”学校とスクールカウンセリング;「チーム学校」と子どものアセスメント;「チーム学校」におけるカウンセリング;スクールカウンセラーのコンサルテーション;「チーム学校」における保護者との連携)
第2部 「チーム学校」におけるさまざまな連携(養護教諭とスクールカウンセラーの連携;いじめ予防の心理教育―SNS・ネットいじめと援助要請を中心とした実践;学校マネジメントにおけるスクールカウンセラーと教師の連携;子ども・保護者参加の援助チーム;特別支援教育とスクールカウンセラーの連携;危機状況における支援)
著者等紹介
半田一郎[ハンダイチロウ]
子育てカウンセリング・リソースポート代表、茨城県公立学校スクールカウンセラー。日本学校心理学会常任理事。学校心理士スーパーバイザー。臨床心理士。公認心理師。1969年、高知県生まれ。1995年より現在までスクールカウンセラーとして51校の小中高校で活動(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
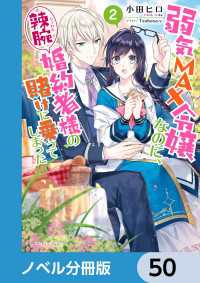
- 電子書籍
- 弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭…
-

- 電子書籍
- 多田あさみ グラビアン砲充填120% …
-
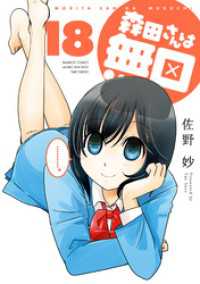
- 電子書籍
- 森田さんは無口 (18) バンブーコミ…
-

- 電子書籍
- 聖霊狩り いにしえのレクイエム 集英社…