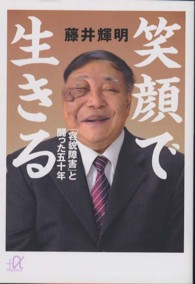内容説明
思いやりを持ちながらかげぐちを言い、優しい自分であろうとして人を傷つけ傷つき、わかりあおうとするから一緒にいられなくなる。―私たちが気づかずに行っている「他者といる技法」を繊細に問う「コミュニケーションの社会学」。
目次
序章 問いを始める地点への問い―ふたつの「社会学」
第1章 思いやりとかげぐちの体系としての社会―存在証明の形式社会学
第2章 「私」を破壊する「私」―R・D・レインをめぐる補論
第3章 外国人は「どのような人」なのか―異質性に対処する技法
第4章 リスペクタビリティの病―中間階級・きちんとすること・他者
第5章 非難の語彙、あるいは市民社会の境界―自己啓発セミナーにかんする雑誌記事の分析
第6章 理解の過少・理解の過剰―他者といる技法のために
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
アルピニア
54
著者は、この本は「弱者」でも「改革者」でもなく「社会の中にいて違和も利益も感じている人」の立場から書いたものと述べている。読んでいて心に刺さることが多いのは、私が正に中にいる人間だからだ。衝撃だったのは第4章。モッセを引用したナチズムについての考察に、自分もその場にいたら支持していたのではと恐ろしくなった。最終章では、他者といるために、「理解」に囚われず他の方法を開く必要性が述べられている。わかった気にならず、わからないから拒絶するのでもなく「わからない他者といっしょにいる方法」を考え続けていきたい。→ 2021/08/16
Bartleby
19
『「理解」とは「わかられたい」水準まで「わかってくれない」苦しみと同様に、その水準以上に「わかられすぎる」苦しみを生むものである。おそらく「理解」とはそういうものだ。いつでも「過少」になるか「過剰」になるかしてしまう。「わかられない、ちょうどいいほどわかられる」こと、「望みどおりに理解される」ことを望むこと、この稀有を望むことを、厳しいこころをもった人々はふつう「甘え」と呼ぶのである。』2013/12/27
テツ
18
『他者』に関する論考集。現代社会では相互理解が何よりも大切であり誰もが他者を理解しようと努めなければならないという呪いが蔓延しているけれど、それによって苦しんでいる方って山のように存在しているよな。理解できない他者と円満な関係を築くための方法。自分を理解して欲しいなどという無理難題を他者に求めないための心構え。本来若者たちにはそうしたリアルな日々で役立つ知恵こそ教えなければならない筈なのに、夢物語をさも現実のように語るから犠牲者が生まれてしまう。どちらにせよ他者に理解を求めるな。その上で関係を構築しよう。2022/09/15
井の中の蛙
9
「私」の、「他者」の、「社会」の分からなさを感じた。いるためにいることを許容できるように。2025/03/12
毒ドーナツを食べたいな
9
国民の教科書に推したい◆「相互承認」「逸脱者の排除」について書かれています◆社会生活において明文化されていないルールを順守するマジメな人たちにとって「村八分」も「いじめ」も成員にとっては合理的な行動なのだ。なぜならば、フリーライダーを徹底的に排除することが成員全体の利益につながることを(無意識的に)理解し行動に移しているにすぎないからだ。 ◆ここでいうフリーライダーとはちょっとした苦役(「思いやり」という相互承認)を放棄した人たちのことである◆関連著者:ロナルド・D・レイン2015/03/05