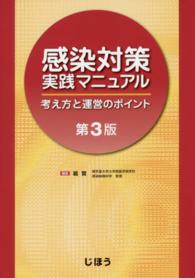出版社内容情報
初・中級向け定番テキスト、待望の改訂版!近年の途上国の実態をふまえ内容を刷新し、最新の実証手法を解説する新章を追加。
序 章
本書のねらい
開発への遠い道程を手を携えて
本書の構成
第1章 膨張する開発経済学
1.1. 開発経済学とは何か?
1.2. 開発経済学の定番:1940~60年代
1.3. 輸出指向工業化と国際経済学:1970年代
1.4. 構造調整の時代:1980年代
1.5. 膨張する開発経済学
第2章 1人当たり所得と貧困・不平等
2.1. なぜ1人当たり所得か?
2.2. 1人当たり所得からこぼれ落ちるもの
2.3. 所得だけが生活水準を決めるわけではない
2.4. 平等な社会かどうか
2.5. 貧困指標
2.6. 国レベルの成果を測るためのマクロデータ
2.7. おわりに
第3章 開発政策のインパクトを測る
3.1. 政策のインパクトを測るためのミクロデータ
3.2. 客観的な政策評価の基本的考え方
(1) 「ナイーブな比較」の問題
(2) 二重差分
3.3. 計量経済学的手法によるインパクト評価
3.4. ランダム化比較実験(RCT)
3.5. 行動経済学的視点
3.6. おわりに
第4章 零細自営業者や小農の経済学
4.1. リキシャ引きのミクロモデル
4.2. ハウスホールド・モデルによるアプローチ
4.3. 市場需要変化の影響
4.4. 賃労働市場との関係と人的資本
4.5. 小農の賃労働市場へのかかわり
4.6. ハウスホールド・モデルの強み
付論 自営業者の主体均衡
(1) 主体均衡の特徴
(2) 市場需要変化の影響
第5章 途上国の信用市場
5.1. 信用の経済的役割(1):生産資金の調達
5.2. 信用の経済的役割(2):消費の平準化
5.3. 信用の経済的役割(3):消費平準化を通じた生産投資推進
5.4. ミクロの信用制約とマクロ経済
5.5. 途上国の信用市場の特徴
5.6. 信用と債務不履行
5.7. 非対称情報下の逆選択とモラルハザード
5.8. 信用市場、貧困、非対称情報
付論 信用の経済効果のモデル分析
(1) 生産信用
(2) 消費平準化のための信用
(3) 消費平準化と生産投資
第6章 貧困層の賃金はなぜ低いままか
6.1. 労働供給の基本モデル
6.2. 賃金の決定要因:労働生産性
6.3. 労働生産性の決定要因としての賃金
6.4. 人的投資と労働生産性・賃金
6.5. 児童労働と人的投資
6.6. 一国内の賃金格差
6.7. 人的資本蓄積、経済成長と国際賃金格差
第7章 貧困の罠からの脱出
7.1. 何から何へジャンプするか
7.2. 規模の経済の具体例
7.3. 規模の経済と市場均衡
7.4. 《むだ》と補完性
7.5. 貧困の罠からの脱出
第8章 技術革新・普及とその制度
8.1. エイズ等感染症と特許
8.2. 技術革新の理論
(1)経済発展と技術革新
(2)知識という資本としての技術
(3)公共財としての知識
8.3. 特許制度の意義
8.4. エイズ治療薬・予防薬開発の課題:技術開発と普及のトレード・オフ
(1)エイズ治療薬価格と開発のインセンティブ
(2)研究開発促進のためのプッシュ・プル政策
(3)エイズ、結核、マラリア治療薬・予防薬に対するプッシュ・プル型支援
8.5. 競争と技術革新のタイプ
8.6. 途上国への技術移転と経済成長
8.7. おわりに : 技術革新・普及と制度
第9章 貧困層への援助
9.1. 貧困削減政策の必要性
9.2. 開発目標としての貧困削減
(1) 開発援助の潮流変化
(2) 世界銀行報告書に見る貧困観と貧困削減政策
9.3. 貧困層への「ターゲティング」
9.4. 貧困層への所得移転政策
9.5. ワークフェア・アプローチによる貧困削減政策
9.6. 貧困層への効果的な援助に向けて
第10章 マイクロクレジットの経済学
10.1. グラミン銀行が注目された理由
10.2. マイクロクレジットの実態:初期のグラミン方式
10.3. マイクロクレジットのメカニズム
(1) グループ融資:相互選抜
(2) グループ融資:相互監視
(3) グループ融資:履行強制
(4) 逐次的融資拡大
(5) 返済猶予期間なしで回数の多い分割払い
10.4. 初期のマイクロクレジットの課題
10.5. マイクロクレジット研究の新潮流
10.6. 課題を越えて
付論:相互監視によってモラルハザードが解消される数値例
第11章 共同体と開発
11.1. 共同体に着目する意義
11.2. 貧困と環境悪化の悪循環
11.3. 「コモンズの悲劇」の基本モデル
11.4. 共有資源維持・修繕の過少投資
11.5. 国家管理か私有化か
11.6. 共同体のもとでの協力
11.7. 経済開発における地域共同体
11.8. 環境問題と共同体の今後
第12章 開発援助とガバナンス
12.1. 汚職の本質とガバナンス
12.2. ガバナンスの程度を測る
指標1:実感汚職指数
指標2:世界銀行の国別政策・制度評価(CPIA)指数
12.3. 賄賂と資源配分
12.4. ガバナンスを改善するために
12.5. 開発援助の潮流変化
(1) 目的の明確化:PRSP、ミレニアム開発目標と持続可能な開発目標
(2) 手続きの共通化:援助協調
(3) 債務救済
12.6. おわりに:開発援助とガバナンス
第13章 グローバリゼーションと途上国
13.1. グローバリゼーションのメリット
(1) 地球規模の効率化
(2) 国際的な所得の平等化
13.2. グローバリゼーションのデメリット
(1) 一部の国民の所得減少
(2) 外国政府・企業による支配
(3) その他の懸念
13.3. グローバリゼーションの利益を途上国へ
(1) グローバリゼーションと貧困削減
(2) 国際協力を伴うグローバリゼーション
(3) グローバリゼーションは自動的に進むか?
13.4. 援助疲れの時代に
参考文献
あとがき
増補改訂版あとがき
索 引
COLUMN
1 N村の15年:タイ
2 銃口とベールの向こう側:パキスタン
3 地主の大うちわ:パキスタン
4 農村でのお金の貸し借り:ミャンマー
5 やればできるはず:ナイジェリア
6 労働は資本を代替する!:バングラデシュ
7 さらけ出す人々:バングラデシュ
8 謎解き2題:パキスタン、ミャンマー
9 田植えの風景:日本・ミャンマー・パキスタン
黒崎 卓[クロサキ タカシ]
一橋大学経済研究所教授
山形辰史[ヤマガタ タツフミ]
日本貿易振興機構アジア経済研究所開発スクール事務局長
内容説明
定番テキスト、待望の改訂!RCTや行動経済学的実験など、進展著しいミクロ実証手法の解説章をはじめ、最新トピックスを加えた決定版。
目次
膨張する開発経済学
1人当たり所得と貧困・不平等
開発政策のインパクトを測る
零細自営業者や小農の経済学
途上国の信用市場
貧困層の賃金はなぜ低いままか
貧困の罠からの脱出
技術革新・普及とその制度
貧困層への援助
マイクロクレジットの経済学
共同体と開発
開発援助とガバナンス
グローバリゼーションと途上国
著者等紹介
黒崎卓[クロサキタカシ]
1964年生まれ。東京大学教養学部卒業。スタンフォード大学でPh.D.を取得。現在、一橋大学経済研究所教授。著書:『開発のミクロ経済学―理論と応用』(岩波書店、日経・経済図書文化賞、国際開発研究大来賞)ほか
山形辰史[ヤマガタタツフミ]
1963年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。ロチェスター大学でPh.D.を取得。現在、日本貿易振興機構アジア経済研究所開発スクール事務局長・教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うーひー
寝子
ぬめぬめ
とある本棚
笠井康平
-

- 洋書電子書籍
- Acupuncture and Ost…
-

- DVD
- 子連れ狼 第八巻(1)