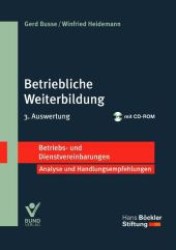内容説明
「ゆとり教育」「学力低下」に揺れる日本の教育。もはや「理想論」を振りかざしている場合ではない!教育を経済学で考えると意外な真実が見えてくる。これまでになかった、目から鱗の教育論。
目次
第1章 教育への経済学的視点
第2章 教育は投資か消費か
第3章 夢または勘違いが支える教育需要
第4章 教育はどこまで成果を挙げられるか
第5章 成長を促し、格差を広げる教育
第6章 経済学から見た教育改革
著者等紹介
小塩隆士[オシオタカシ]
1960年京都府生まれ。1983年東京大学教養学部(国際関係論)卒業。同年、経済企画庁入庁。1989年イェール大学経済学修士号取得。1991年J.P.モルガン入社。1994年立命館大学経済学部助教授。1999年東京学芸大学教育学部助教授、現在に至る。2002年大阪大学博士号(国際公共政策)取得
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
武井 康則
9
教育を受ければ幸せになれるのか、収入は増えるのか、必ず学力は身に着くのか、つかないのならばその損失は。そもそも学力とは何なのか。公教育で賄われる税金は無駄でないのかとか、教育を考えるにはまず教育全般にわたっての定義がなさすぎる。施策として教育を取り上げる割にその結果を検証していない。データがない。だから学問として教育を考えられないと後書きで書いている。また確かにみなが教育を信じて受けさせればコモンセンスは安定するだろうが、自らの失敗からだろうが、一部の親が「学びからの逃避」を始めている。→2025/01/26
takao
3
ふむ2024/02/25
kishikan
2
「〇〇の経済学」という本は山ほどあるけれど、この「教育を経済学で考える」は非常に面白い。教育関係者によっては「教育問題は経済的視点で述べられるべきではない」とおっしゃる方も多いけど、教育にまつわる問題を経済学視点(つまり社会科学の視点での分析)で考えることは非常に有用である。学力問題についての記述や公的教育の在り方なんかは、そういう批判的な教育関係者からも支持されるんじゃないでしょうか。教育行政に携わる人には是非読んでもらいたい。
Takanobu Y
1
シンプルで分かりやすい。賛同できない部分もあるが概ね納得できる仕上がりになっている。学校教育問題で語られる議論の対象は、前提条件から間違っていることに気付かされる。優れた才能もなく、勉強もあまり好きでない、普通の子供たちのための公教育。しかし、生まれ持った環境によって学力は左右されるという問題を本質的に抱えている。現実には、そこに蓋をした議論でいっぱいなのだが・・・さらには、教育によって格差が広がっていくという矛盾。教育に対する幻想を、そろそろ捨て去る時期なのではないだろうか。2015/12/26
KK
0
今年最も勉強になった本かもしれない。経済学の視点から教育の負の側面に触れ、あるべき教育の姿にたいするヒントが描かれている。2017/12/24
-

- 和書
- 楕円曲線論入門