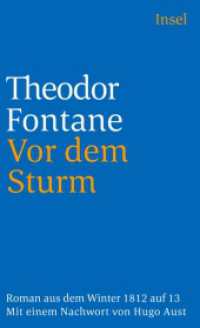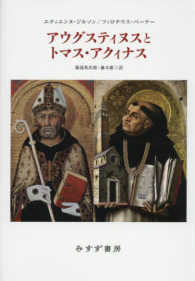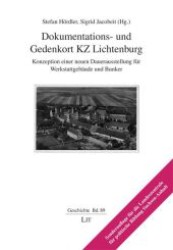出版社内容情報
理論偏重から実証分析重視へと変貌を遂げた経済学。その変貌の経緯と、理論と実証の狭間で苦闘してきた経済学者たちの足跡を追う。
内容説明
理論偏重から実証分析重視へ。そのはざまで苦闘してきた経済学者たちの足跡を追う。
目次
序章 データの波にのまれる経済学界
第1章 ノーベル経済学賞と計量経済学、つかず離れずの歴史
第2章 主役に躍り出た実証分析
第3章 因果推論の死角
第4章 RCTは「黄金律」なのか
第5章 EBPMの可能性と限界
第6章 消えゆくユートピア
著者等紹介
前田裕之[マエダヒロユキ]
学習院大学客員研究員、川村学園女子大学非常勤講師、NIRA総合研究開発機構「政策共創の場」プロジェクト・パートナー。1986年東京大学経済学部卒、日本経済新聞社入社。東京経済部記者、経済解説部編集委員などを経て2021年に独立し、研究・教育や執筆活動に取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
93
最近の経済学の動向を明らかにしてくれて、いい本だと思います。「世界最高峰の経済学教室」という本を少し前に読んだのですが、経済学のカタログのような感じで若干期待外れだったのと比べると非常に参考になりました。最近の動向としてのデータをどのように利用していくのかがよくわかり確かに実証分析という面では面白い気がします。RCT(ランダム化比較試験)とEBPM(証拠に基づく政策立案)の章が非常に面白く読みました。2023/10/29
koji
19
「経済学の壁」の姉妹書。今や経済学は、データ分析を重視する実証研究が花盛り。数式やグラフによる理論研究は(傍目には)退潮を余儀なくされています。本書は、理論VS実証の歴史を丹念に追った労作です。特に、因果推論、RCT、EBPMの項は、先行研究を踏まえ緻密な議論が展開され読み応え抜群でした。私は、読メを始めてから、日経図書賞、その年々の「日経新聞、週刊ダイヤモンドの経済書ベストテン」の書籍からピックアップして読むようにしていますが、今一つ視界不良でした。本書は、その不良な視界を開く灯台守のような1冊。大満足2024/02/09
とりもり
9
経済学の中心が理論から実証分析へとシフトし、近年はむしろ論文が粗製乱造されている状況を通史的に描写する。確かに、最近の経済学書は統計的分析を施して「こんな結果が出ました、統計的にも有意ですー」ってパターンのものが多く、読んだ後に「だから何?」って思うことしきり。実証実験がしにくい経済学においてRCT(ランダム化比較試験)が果たした役割は大きいが、それに依存するあまり、経済学の可能性を狭めているのが現状ではないか。実証分析の結果から本質を見出して新たな理論を構築するような経済学者の登場が待たれる。★★★☆☆2023/11/29
shin_ash
9
「経済学の壁」姉妹本。前著同様に1930年以降の経済学の流れを今回は実証分析系の流れに軸足を置いて解説している。現在位置としてはデータ分析中心の実証経済学が主流の様で、筆者としてはあまり好感を抱いてはいない様だ。本書で意外(違和感)に思えるのは古典統計やRCT、統計的因果推論、果ては機械学習など「それは統計学(に近いの)では?」と思われるものも計量経済学に入ってしまっていることだ。逆に言えば計量経済学の文脈で分析手法が開発されてきたとの立場をとる。確かにそう言う側面はある。因果推論の解説本では“外生的” 2023/08/14
Kiefer
0
特に第5章が面白く感じた。EBPM(エビデンスに基づく政策立案)の課題として、研究者は日本の行政記録情報を使えず、それとは別にデータを収集する必要がある。行政が研究者にデータを提供ことも、政策効果の検証を依頼することも少ないらしい。学術論文がそのまま政策立案につながるわけでもない。EBPMの動きには期待したが、意外と官学の隔たりは大きい。 (備忘録に参考レポートURL) https://www.npi.or.jp/research/npi_pp_takahashi_202003.pdf