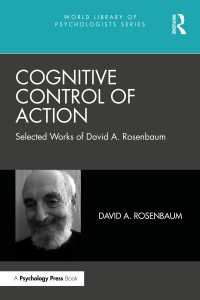目次
第1章 色の持つ力
第2章 色と生活
第3章 色の見え方
第4章 色とイメージ
第5章 配色のルール
第6章 即効!カラーイメージチャート
第7章 色彩計画と色彩戦略
著者等紹介
南雲治嘉[ナグモハルヨシ]
デザイナー。日本カラーイメージ協会理事長。1944年東京都生まれ。金沢美術工芸大学産業美術学科卒業。デジタルハリウッド大学デジタルコミュニケーション学部教授・先端色彩研究室長。担当はデザイン概論、発想概論、色彩論など。90年に株式会社ハルメージを設立。アートディレクター、グラフィックデザイナーとして仕事をするかたわら、ベーシックデザインと色彩に関する研究を進め、常用デザインと色彩生理学を提唱している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Cambel
10
色彩学のことが知りたくて、勉強のために読了。色は光、光は電磁波。そう考えると超波長の赤が浮き上がって見えるのも、短波長の青が後退して見えるのも、物理型的に理解できた。 美術の教科書でよく見る「色相環」とスペクトルは科学的には一致しないんだそうな。赤と紫は色相環では隣同士だけど、スペクトルでは端と端で一番離れている。へえ〜、そうなんだ。2017/04/29
綾瀬ちかこ
2
色彩検定やカラーコーディネーター検定の入門書のような感じ。硬い文体だけれど、知識として知るにはいいとっかかりになる一冊でした。2012/11/20
monotane
1
筆者は「雑学ではない体系的な知識を学ぶ人のためにこの本を書いた」という。確かに全くの初心者向けと言うよりはある程度色彩の知識を持った人向けだと感じた。だが構成は一つの項目が2,3ページで終わる程度の文章量で、ブログやメルマガでも読んでいるかのようだった。片手間に読むのにはいいが。さらに内容は「配色について」と題しているが「色彩の雑学」が大半を占めていたように思う。個人的には流行色の話が面白かった。しかし出典が曖昧で深く調べる道筋がない。体系的な知識を身につけさせたいなら文献を明記すればよいのにと思った。2012/03/05
蕃茄(バンカ)
0
「彩度」とか「補色」とか基本的な用語に対する説明無し。それは知ってる前提という事かもしれないけどそういう知識を真に理解している人間にはそもそもこういう本は必要ないと思う。「雑学的な知識より使える知識」と言っても一つの項目に対する文章量が少ないので皮相的。「使えない理論はいりません」ってあとがきにありますが何故こうした配色が成り立っているのか?という理論を飛ばして即使える配色チャートだけ教えてるから教え子が現場で0からデザインを作るのに苦労してるんじゃないですかねぇ。2016/11/11
にしぞのだいすき
0
使える配色チャートなる、迷える子羊救済のためのページあり。私は誰かの指示を仰いだりするの好きなので、この手の例は助かります。2013/02/21