出版社内容情報
新しい知のトレンドを若き俊英が初めて世に問う
目次
序章 「心」と「脳」を「クオリア」が結ぶ
1 認識は「私」の一部である
2 「反応選択性」と「認識におけるマッハの原理」
3 認識の要素
4 相互作用同時性の原理
5 最大の謎「クオリア」
6 「意識」を定義する
7 「理解」するということはどういうことか?
8 新しい情報の概念
9 生と死と私
10 私は「自由」なのか?
終章 心と脳の関係を求めて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
48
生物学の参考文献。脳科学であっても、突き詰めていけば哲学にたどりつく。「クオリア」という概念はやはりとても面白い。誰もが共感できる内容だと思う。2015/05/27
ゆか
24
クオリアとは言葉では表すことの出来ない、いわゆる「感じ」。何か嫌な感じ。とか、ワクワクする感じとか。それを言葉で説明するわけだから、本書はそれなりに難しくなる。たまに何を言ってるのか分からなくなることもしばしば…(笑)物理学や心理学に興味のある人ならば、面白いかも。でもこのクオリアを自分でコントロールする事ができれば、みんなが平和な精神状態になれそうな気がする。2015/12/30
ないとう
17
クオリア: quails [哲学用語] 1.特質:事物としては独立きて存在する普遍的な本質 2.(明確な特質を持つ)感覚データ2015/09/09
テツ
16
ぼくたちは簡単に日常生活の中で心という単語を口にするけれど人間の身体のどこを抉っても見つからない心。脳味噌のハタラキのメカニズムはぼんやりと解明されても個人の中で湧き出るクオリアは各々の主観としてしか認識できないために科学的に説明できるかどうかすら定かではない。そんなあやふやな心に振り回されるなんて馬鹿げたことだなあと思う。みんな心穏やかだったり心を痛めたりしながら日々を生きていく。その穏やかさや痛みって蜃気楼のようなとりとめのないものなんだな。そうしたものに縛られずに生きていきたいものです。2020/07/13
Koichiro Minematsu
16
ストーン・ヘンジから始まり、最後はパルテノン神殿のケンタウルスとラピタイ人の彫像まで、漸く読み終えた。理解力の乏しさを痛感すると共に、茂木先生の脳科学の深さに驚くばかり。クオリアという心と脳をつなぐ、人が持ち合わせている質感は、人の成長、進化に強く影響している。生産性のある、感情豊かに、脳が機能を発揮できる生活に注意を向けたい。2017/09/30
-
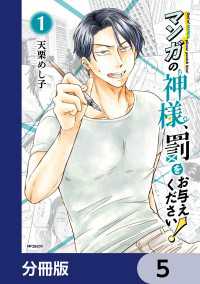
- 電子書籍
- マンガの神様、罰をお与えください!【分…
-

- 和書
- ロングマン現代実証英文法






