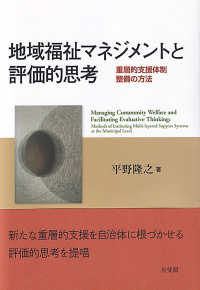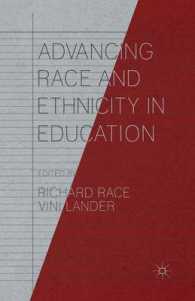出版社内容情報
耐えることができない、すぐ感情的になる、優先順位が決められない、主張だけは強い……。今の新人に抱く違和感。そのルーツとは?
内容説明
我慢することができない、すぐ感情的になる、優先順位が決められない、自己主張だけは強い…。今の新人に抱く違和感。そのルーツは子ども時代の過ごし方にあった。いま注目される「非認知能力」を取り上げ、想像力の豊かな心の折れない子を育てるためのヒントを示す一冊。
目次
第1章 「頑張れない」「我慢できない」―今の子ども時代に足りないもの(注意や叱責に耐えられない若者たち;叱られたことがない ほか)
第2章 早期教育に走る親たち―はたして効果はあるのか(メディアを通して喧伝される早期教育;早期教育に効果はあるのか? ほか)
第3章 幼児期の経験が将来の学歴や収入を決める?(ノーベル賞受賞学者が見出した幼児教育の効果;大きくなってから効いてくる幼児教育の効果とは? ほか)
第4章 子ども時代に非認知能力の基礎をつくっておく(親が子どもとじっくりとかかわることの大切さ;自発性を高める接し方 ほか)
第5章 子ども時代の習慣形成でレジリエンスを高める(読書にみる習慣形成の威力;近代の著名哲学者も習慣形成に言及 ほか)
著者等紹介
榎本博明[エノモトヒロアキ]
心理学博士。1955年東京生まれ。東京大学教育心理学科卒。東芝市場調査課勤務の後、東京都立大学大学院心理学専攻博士課程中退。川村短期大学講師、カリフォルニア大学客員研究員、大阪大学大学院助教授等を経て、現在MP人間科学研究所代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲンキ
あすなろ@no book, no life.
たまきら
レモン
ta_chanko