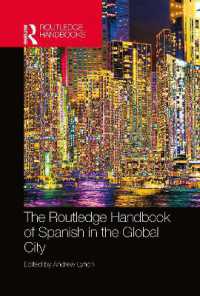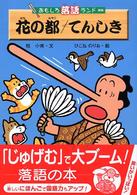内容説明
万物に質量を与える素粒子、ヒッグス粒子の存在が提唱されておよそ半世紀。欧州合同原子核研究機構(CERN)は、ついにヒッグス粒子と見られる新粒子を「発見」した。ヒッグス粒子とは何なのか、どのように見つけ出されたのか、物理学の次の課題は…。尽きない疑問をわかりやすく解説する。
目次
第1章 素粒子って何?
第2章 ヒッグス粒子とは何か?
第3章 宇宙はどのようにして作られたのか?
第4章 粒子の実験に使う「加速器」とは?
第5章 実験装置の中を探ってみよう
第6章 ヒッグス粒子発見は物理学の未来への第一歩
著者等紹介
竹内薫[タケウチカオル]
1960年生まれ。サイエンス作家。東京大学教養学部卒、同理学部物理学科卒。マギル大学大学院博士課程修了(理学博士)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ntahima
39
今、科学界でホットな話題。素粒子論については一般書を何冊か読んだが、この本が一番読み易い。但、読み易いと言うことは難しい部分を省略しているということであり、最初の一冊として最適かと言うとそうでもない。本書のメインテーマは『全ての物質を構成する“素粒子”に“質量を与える”粒子』と呼ばれるヒッグス粒子についてである。わからないなりに読み進めると、最後に(飽くまでも)『素粒子に質量を生み出すもの』であり『ヒッグス粒子が与える質量は、たったの2パーセント?』とある。完全に騙された。これって一種の叙述トリックだね。2012/09/03
ちくわん
18
2012年8月の本。素粒子については第2章まで。あとは宇宙創成と加速器。J・J・サクライ氏は知らなかった。最後の方に出てきたILC(国際線型加速器)。建設費だけでも8000億円。アメリカにあったフェルミ国立加速器研究所の加速器は資金難で30年で運転停止。北上山地に本当に誘致するのだろうか?加速器は何度も「過疎区」器に変換された。まぁ、そうではあるが、どうなんだろう?2021/02/28
白義
10
分かりやすさに特化した竹内薫らしく、恐らく正確に理解すると途方もないであろう素粒子の世界をこの上なくはっきりとイメージさせてくれる。ヒッグス場というプールに素粒子が捕まり、自由に動けなくなる=素粒子に質量が生まれる。実際は素粒子の質量は宇宙全体の質量からするとかなり少ないんだけど、それでも大変な存在であり、もし予言されているだけのヒッグス粒子がはっきり確認されたら驚天大ニュース、ということ。素粒子物理学の基本から語ってくれる丁寧さが門外漢にはありがたい2013/09/28
takao
3
ふむ2024/05/24
毎時のおやつ
3
物理学者は水飴の例えを嫌うらしい。質量には慣性があるので水飴だと慣性を表現しない。大栗博司の「強い力と弱い力、ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く」を読んだ後なので、わかりやすくはあるがエキサイティングではないという感じになってしまった。一方で新しい知見もあった。2017/09/28