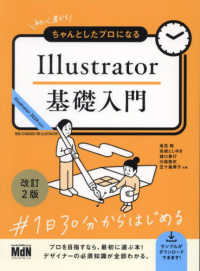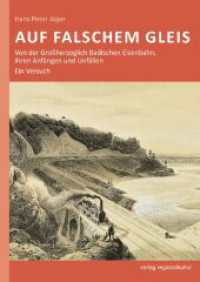内容説明
「銭の単位は十進法、金は四進法と十進法、銀は秤で量って使う」「お茶や薬は銀、日用品は銭で支払う」―やたらと複雑だった江戸時代のお金は、いったいどのように作られ、稼がれ、使われていたのか。意外に知らない江戸の通貨事情をユニークなエピソードとともに紹介する。
目次
序章 江戸時代はお金の時代
第1章 複雑だった江戸時代のお金―金・銀・銭の三貨幣
第2章 町人のお金の稼ぎ方・使い方
第3章 お金に追いまくられる武士
第4章 お金と貿易・お金の改鋳
第5章 明治になって
著者等紹介
鈴木浩三[スズキコウゾウ]
博士(経営学)、東京都水道局多摩水道改革推進本部調整部管理課長。1960年東京生まれ。83年中央大学法学部卒業。2005年筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業科学専攻修了。83年東京都入庁、環境局総務部副参事、水道局職員部労務課長などを経て現職。2007年日本管理会計学会「論文賞」受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
99
江戸時代ではおカネって、結構複雑です。「ただ持っていればいい」とか、「誰でも使ってもいい」というわけでなかったらしい。裏店に住む「はっつん、熊公」が、何の前触れもなく、小判を使うと、「零細商人→一般商人→両替商→奉行所」というルートで足がついて、たちまちしょっぴかれることもあったとか。そういうわけで、庶民が「ねずみ小僧」などの義賊に、 大商人から盗んだ小判をばらまいてもらっても、実は大して嬉しくなかったらしい。2013/10/15
Willie the Wildcat
55
米本位経済から貨幣経済への変化。『信用』尺度の変化と解釈。象徴は包金/包銀。御用達町人故の利権と贈収賄。どの時代も構図は同じ。後藤庄三郎かぁ、やるなぁ家康。現代と遜色のない仕組みの中、休株/明株と弘メが興味深い。日本商文化の礎を感じる。加えて、七分積金などに垣間見る社会保障制度も、現代の国民皆保険に繋がる。個ではなく社会という概念が養われていく過程とも言える。それにしても、幕末の不平等条約等による諸外国による搾取の件は、頭でわかっていても毎度不快だなぁ。2016/11/10
井月 奎(いづき けい)
32
生まれ変わったらハイ・カーストのインド人か江戸の町人になりたかったのですが、私のつたない頭では江戸の町人は難しいかもしれません。なんせお金が三種類あって、つまり金、銀、銅なのですが、それぞれが単独して流通していたらしいのです。払い方も金極、銀極などのしばりがあり金で払わなければいけない、銀じゃなきゃ受け取らねえぞ、この野郎、のようなことだったらしいのです。しかも銅は紐に九十六枚通すと百文として流通できるなど複雑怪奇なのです。こりゃあ、ハイ・カーストのインド人になってすべてを人にやってもらわなきゃ、ですね。2018/06/20
びいたな
2
知らぬことだらけ、面白かった。それぞれ価値が変動する金、銀、銭や為替取引、信用取引、先物取引や貿易。このような高度な経済を持つ時代を経ているからこそ明治の躍進もあったんだなと個人的には納得した。全体観を把握できるような年表や写真などがまとまった図録があれば併せて見てみたいと興味を持った。2012/03/04
Keikoh
1
徳川家康による一連の通貨統合は、貨幣経済が発達するきっかけになりました。そのとき作られた「お金」の制度はとても複雑でした。複雑なお金によって、一つのモノやサービスに対して地域的にも季節的にも多様な経済的評価がなされ、それが経済のダイナミズムを刺激していた。さらに、人々がさまざまな工夫や知恵をこらした経済活動を繰り広げる世の中だった。こうした”一物多価”と競争の積み重ねが、経済の活力に結びついたといえるでしょう。2024/11/18